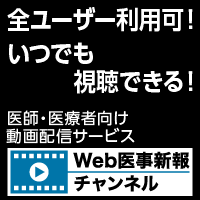お知らせ
【識者の眼】「世界で展開されるプライマリヘルスケアの再登板」中村安秀
No.5134 (2022年09月17日発行) P.58
中村安秀 (公益社団法人日本WHO協会理事長)
登録日: 2022-09-05
最終更新日: 2022-09-05
- コーナー: OPINION
- 医療界を読み解く[識者の眼]
国際社会においてポスト・コロナ(COVID-19)の保健医療体制を議論する中で、プライマリヘルスケア(primary health care:PHC)という言葉を耳にする機会が増えた。
1978年にアルマアタ宣言で謳われたPHCは、多くの開業医や総合診療医が提唱する日本のプライマリケア医とはまったく異なる概念である。PHCがカバーするのは、一次医療だけでなく、予防医学、健康づくり、住民のエンパワーメントや権利擁護などを含む、包括的な概念である。そこでは、医師を頂点にしたチーム医療ではなく、住民を主体にし、保健医療関係者だけでなく、教育、社会経済、環境などの他のセクターとの対等な関係性の中での協働作業が前提となっている。
コロナ以前においてPHCを実践してきた世界の多くの国で、その再評価が行われている。たとえばタイでは、コロナによる厳しい外出制限の時期に、母子保健やエイズ対策の保健ボランティアにコロナ対策研修を急遽実施し、コミュニティの中での感染者の発見や予防教育の啓発を行った。パプアニューギニアでは、コロナによる移動制限で医療者が入っていけなくなった村々で、保健ボランティアが簡易な手洗い器具を設置した。イタリアでは、医療崩壊と言われた2020年前半に、数万人規模の病院ボランティア(IT企業や弁護士など職業は様々)が医療機関の仕事を手伝った。
医療者だけで、移動制限や外出制限の中での医療を完結することはできない。だからといって、37.5℃以上の熱が4日以上という目安とともに出された「うちで治そう」というメッセージは、日本の医療体制の弱点をさらけ出したとも言える。
COVID-19により、セルフケアの重要性が一気に認知された。世界保健機関(WHO)は2022年に「健康とウェルビーイングのためのセルフケア介入」というガイドライン改訂版を出した。セルフケアは一人で完結するものではないというのが世界の共通認識である。個人、家族、地域、支援機関(病院、保健所、自治体)の横断的な連携が不可欠である。医療機関や行政と個人・地域の橋渡しとして、保健ボランティアに積極的に活動してもらう仕組みをつくっている国も少なくない。
日本は国民皆保険制度というすばらしい財産があるのだから、「うちで治そう」と突き放すのではなく、行政や医療機関の関わりのもとで、身近な地域の人たちの支え合いの中で療養できるようなPHC体制の構築こそがポスト・コロナの医療体制のひとつの姿であろう。
中村安秀(公益社団法人日本WHO協会理事長)[新型コロナウイルス感染症]