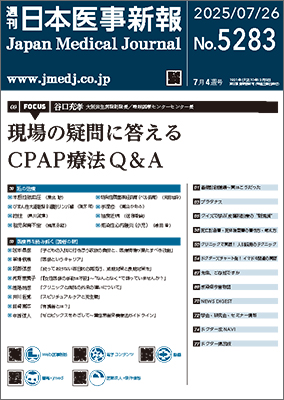お知らせ
【識者の眼】「同一医師の継続診療について」樫尾明彦
No.5278 (2025年06月21日発行) P.59
樫尾明彦 (調布東山病院 内科)
登録日: 2025-04-28
最終更新日: 2025-04-23
- コーナー: OPINION
- 医療界を読み解く[識者の眼]
私事ですが、2025年4月に常勤先を移りました。
これまで常勤で勤務していたクリニックでは8年間働きましたが、同じ環境で継続的に診療をすることについて、(離れてからも含めて)気づいた点を挙げてみます。

メリットについて
同じ環境で長年診療をすることで、職場内外のスタッフや患者さん(家族)と関係性を築き、慣れていくことで、診療を通じて様々なケースを経験して、学べることが挙げられます。ケアの継続性の意義については、国内外の文献1)2)でも指摘されています。
デメリットについて
上記メリットの半面、同じ患者さんを同じ医師が継続して診療することで、認知バイアスの1つである、attribution errorが起こるリスクが考えられます。
たとえば、毎回の診療で、慢性の肩こりを訴えている患者さんが、ある日の診療で、特に左肩が数日かなり痛むと訴えたと想定します。診療した医師は、その左肩関節痛に対して、狭心痛の放散痛を想起せず、きっといつもの肩こりだろうと考えてしまうのが、attribution errorの例です。
また、患者さん側の心理としても、何か新しい症状について、医師から精査を勧められても、医師との関係性が保たれている場合には、「また次回の診療で相談するから」と患者さんが精査を希望しないという傾向も、同一医師での継続診療では強くなる可能性も考えられます。
attribution errorのリンクの中で「正しく診断に近づけなかった場合に、“早合点してしまった”“慎重に鑑別疾患をあげることをしなかった”“次回からは注意しよう”という慣用的表現で振り返るのではなく、“attribution errorを起こしそうになった”と、認知心理学的用語を用いて自己省察できることが望まれる」と紹介されています。すなわち、日常診療でattribution errorは起こりうるものだと、常に念頭に置いておくことが必要と考えられます。
家庭医が異動する要因について
家庭医が勤務先を変更する理由については、トルコの研究3)によると、職場からの距離、新しい関心、バーンアウト(燃え尽き症候群)が主なものでした。
筆者が今回、常勤先を移した理由の1つは、病棟勤務から数年以上離れて、訪問診療(往診)や外来から他院に紹介した患者さんが入院となった場合に、入院先の治療を徐々にイメージしにくくなってきた点でした。そこで、もう一度、外来、病棟、在宅と一連のつながりのある環境に身を置いて仕事をすることで、そのギャップを埋めることができればと考えました。まだまだ新しい環境には慣れず、医師という職業の、いつになっても学び続けていく意義や大変さを感じる日々です。
【文献】
1)栄原智文, 他:ケアの継続性について. 新・総合診療医学 診療所 総合診療医学編. 第3版. 藤沼康樹, 監. カイ書林, 2019.
2)Shumer G, et al:Ann Fam Med. 2025;23(2):151-7.
3)Karayurek Y, et al:Fam Pract. 2021;38(5):556-61.
樫尾明彦(調布東山病院 内科)[医師の異動][ケアの継続性][attribution error]