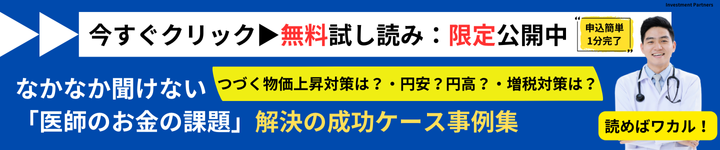お知らせ
米国医療事情[なかのとおるのええ加減でいきまっせ!(338)]
本の紹介は1回だけと決めているのだが、今回の『医療現場は地獄の戦場だった!』は例外的に読売新聞に次いで2回目。ハーバード・メディカルスクール第2の教育病院、ブリガム・アンド・ウィメンズ病院の救急治療室、ERに勤務する大内啓医師の本である。
前半は新型コロナウイルス禍におけるERでの出来事の紹介で、信じられないほど凄まじい。文字どおり息をのむような緊迫感だ。そして、後半はちょっとのんびりと「こうしてアメリカで医師になった」と「日本とはこんなに違う、アメリカの医療」である。
大阪に生まれ、父の仕事の都合で小学校卒業時に米国に渡った大内医師の経験と、日米医学教育・医療事情の紹介なのだが、これがまた、前半に勝るとも劣らぬ面白さ。
英語も日本語も中途半端、「授業のどのポイントがわからないのか、それすらわからない」と大学の学生課に泣きをいれた大内青年が一念発起、23歳から30歳まで死ぬほど勉強して医師になった話、なぜER医をめざしたかの話などは、むちゃくちゃにおもろいのだが、それは読んでもらってのお楽しみ。
入試も含め、米国のメディカルスクール制と日本の医学部の制度の違いがよくわかる。ただ、米国のメディカルスクール生の約4分の1が代々医師の家系、半数以上が全米のトップ20%の収入のある家の子女、というのは日本と同じようなものだろうか。
出身校、ワシントンDCにあるジョージタウン大学メディカルスクールの4年間の学費は、全米のほぼ平均で26万ドルと高額だ。同級生の半数は大金持ちの、半数弱が中流家庭の子女である。しかし、アファーマティブアクションにより、非常に貧しいが賢明な人たちが混じっているのがとてもいい。
難民や、両親の苦労を見てきた人たち、さらには、スラム街に育ち少年院と刑務所での生活の方が長かったヒスパニックの青年まで、なんという多様性。こういった同級生から得る刺激はどれだけ大きいだろう。日本の医学部の均質さとは大きな違いだ。
「努力と実力で上がっていけるのが、アメリカの医学界の素晴らしいところ」と語る大内医師は、終末期医療の「バイタル・トーク(vital talk)」の臨床研究者でもある。患者とのコミュニケーション技術を高める対話技術のことで、米国では医師ら1万人以上が学んでいるという。その内容を知るだけでもこの本を読む価値があるはずだ。
なかののつぶやき
「読売新聞の『本よみうり堂』で、前半の2章、『コロナ最前線のまっただ中へ』と『死の周辺』についてはすでに紹介済みです。ぜひ【地獄の戦場×読売×仲野】で検索して読んでみてください。びっくりしますで、ほんまに」