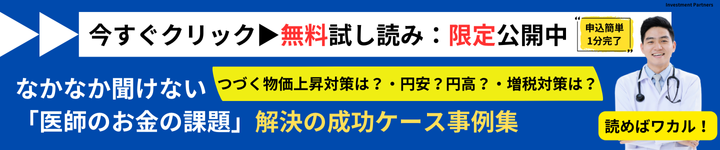お知らせ
マンジュシャゲの方言いろいろ[炉辺閑話]
秋のお彼岸の前後、田舎の河原や土手、墓地のあたりなどに、群れて咲く真紅の花、マンジュシャゲ。真っすぐに伸びた1本の茎の先端から、線条のまっ赤な花弁が円を描いて空を指している。まるで線香花火の火花を逆さまにしたような……。曼殊沙華と書くが、もとは梵語である。
このマンジュシャゲ、地方によっていろいろな名称で呼ばれている。周囲の雑草の中にあって、あまりにも鮮やかな色彩が、人々の眼をどのようにとらえてきたか、その地方の方言は、それを物語っている。近世の「物類称呼」をみると、「伊勢―セソビ。中国・武蔵―シビトバナ、ヒガンバナ、キツネノカミソリ。上総・美作―ユウレイバナ、ヒガンバナ。越後・信濃―ヤクビウバナ。京都―カミソリバナ。大和―シタコジケ。出雲―キツネバナ。尾張―シタマガリ。駿河―カワカンジ。西国―スチゴバナ。土佐―シレイ、シビトバナ、スズカケ」等と出ている。
キツネとかユウレイ、シビトなどと、薄気味悪い呼び名が目につくが、尾張方言となっている「シタマガリ」は、わが因幡でもよく耳にする。八頭郡一帯に広く用いられているが、中には「ヘビノシタマガリ」と言う念のいった所もある。
ところで、この「シタマガリ」というのは、どのような意味が込められているのだろうか。これは根の下のほうが曲がっているということではない。おそらく、ずっと古く、野草を食用にしていた時代の名称ではあるまいか。この根はいわゆるタマネギやユリのような鱗茎である。ところが、このマンジュシャゲのそれは毒性を持っているのだ。これは7回ほど水洗してその毒性を除けば、けっこう澱粉食料となるのだが、それを知らない昔の人は、苦いクワイでも食べられるのだからといったようなことで、これを食べた。が、食べてみると、その毒性は「舌が曲がる」ほどであった。つまり「シタマガリ」だった、とそれがいつのまにやら名称化され、子孫に伝えられていった、と考えられる。
大和方言では「シタコジケ」だ。「コジケ」は「凍てつく・麻痺する」意。つまり、舌がしびれる、という意味になろう。実際に食べたことがないからわからないが、相当すごい猛毒ではなかろうか。それを試行錯誤の体験者であるわれわれの祖先が、方言として子孫に教えてくれているのである。