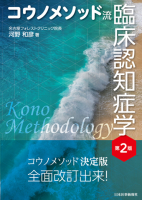お知らせ
【識者の眼】「認知症に関する新しい検査」内田直樹

認知症診療の現場では、「改訂長谷川式簡易知能評価(HDS-R)」が長らく用いられてきた。しかし、開発から約50年が経過しており、医療技術の進歩や社会の高齢化に伴い、より迅速で客観的な検査法の必要性が高まっている。
このような背景の中、2025年1月にフューチャー株式会社と株式会社アイ・ブレインサイエンスが共同開発した「ミレボ®」が、大塚製薬株式会社から販売された。

ミレボ®は、アイトラッキング技術を活用した神経心理検査用プログラムであり、タブレット端末にインストールされたアプリを使用し、約3分で簡便に検査を行うことが可能であるとのこと。被検者が画面上の質問に対して正解の箇所を見つめることで、視線データが自動的に収集・スコア化され、検査者の知識や経験に依存しない客観的な評価が可能とされている。
ミレボ®の主な利点として、短時間での検査実施、検査者および被験者の負担軽減、そして結果の客観性が挙げられる。従来のHDS-Rやミニメンタルステート検査(MMSE)では、検査者の熟練度や被検者の心理的負担が結果に影響を及ぼす可能性が指摘されていた。一方、ミレボ®は視線計測を用いることで、これらの課題の克服をめざしている。
しかし、ミレボ®がHDS-RやMMSEの役割を完全に代替することはないと考える。なぜなら、HDS-RやMMSEでは各項目の得失点によって、脳の障害部位を推定し病型診断の参考にすることができるためである。
また、簡便な検査法の普及に伴い、認知症の診断が容易になる一方で、安易な薬物処方や過剰診断のリスクも懸念される。認知症の診断において、認知機能障害だけでなく生活障害の評価も重要である。生活での困りごとについて聴取し、その背景にある認知機能障害と環境の影響を見定め、生活の質をいかに改善するかを話し合っていくことが認知症診療の基本である。さらに、アルツハイマー型認知症と診断し、抗認知症薬を処方する前に、甲状腺機能低下症や正常圧水頭症などの治療可能な認知症を除外することも重要である。
ミレボ®の登場は、認知症診療に新たな選択肢を提供する。また、近い将来には、テクノロジーを活用した新たな検査機器が複数登場することは間違いない。しかし、その活用にあたっては、利点と課題を十分に理解し、適切な判断を行うことが必要である。
内田直樹(医療法人すずらん会たろうクリニック院長)[認知症診療][認知症検査法]