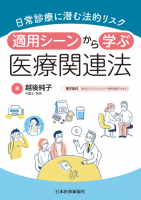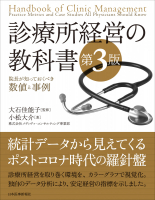お知らせ
【識者の眼】「病院の建設費について考える」伊関友伸
病院建設費の増加が止まらない。独立行政法人福祉医療機構の『2023年度 福祉・医療施設の建設費について』によると、機構が貸し付けをした病院施設の平米当たりの建設単価が、2012年度の22.0万円から2023年度の41.1万円へと2倍近くに増えている。
東日本大震災の復興や東京オリンピックの開催、新型コロナ、ウクライナ戦争、10%への消費税増税、都市再開発や半導体投資などの巨大プロジェクトの実施、円安による輸入資材の高騰、少子高齢化による建設人材不足などにより、病院の建設単価は急上昇してきた。

筆者は、今後も建設費は上昇することはあっても下落することはないと考えている。その要因は建設業就労者の減少である。1997年の685万人をピークに2019年までは500万人程度で推移してきたが、2020年以降減少傾向にあり、2022年は479万人まで減少している。
建設業は就業者の高齢化が進んでいて、2022年における55歳以上の就業者は35.9%、29歳以下は11.7%である。今後、18歳人口が減少し、建設業への新規就業者が頭打ちになる中、高齢の就業者が引退することで、深刻な人材不足を起こす可能性が高い。新規就業者が建設業界に就業するためには、業界として社会保険への加入や適切な給料の支給など、勤務環境の改善が必要となる。2024年4月には、医師と同様に建設業界に時間外労働時間の上限規制が導入されている。待遇改善の費用は、当然建設コストの増加につながる。
建設費の高騰により、建て替えを断念する病院が相次いでおり、さらには医療継続を断念する病院も出てきている。病院の建設単価の上昇は、わが国の医療に深刻な影響を与えている。
少子高齢化が本格化するこれからの時代は、これまでの指名競争入札などの競争性の導入は限界を迎えている。18歳人口が多く、若年労働者の雇用がしやすかった時代は、競争で仕事を取ることができた。しかし、現在の人手不足の時代は、競争性を発揮して新たに仕事を取り、余分に仕事をする人的余裕はない。これからの建設発注は、複雑で施工の難しい設計を競争入札で安く建設させることはできない。シンプルで建設しやすい設計の病院を適正な金額で発注する以外はない。
2024年度の報酬改定はプラス改定であったが、医療従事者への処遇改善に対してのものであり(それもまったく不足するものであったが)、老朽化した病院施設の建て替えに対するものではない。病院の建物は、日本国民にとって重要なインフラというべきものであり、インフラ維持のために国の財政的支援が必要と考える。
今後の病院経営が不透明な中で、病院を建て替えることはとても困難な時代となっている。その中で、病院を建て替えていくためには、様々なリスクを考え、知恵をしぼった建設計画が求められる時代となっている。
伊関友伸(城西大学経営学部マネジメント総合学科教授)[病院経営][建設費]