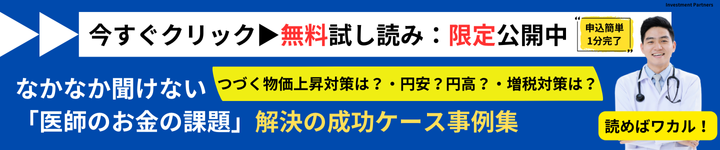お知らせ
庄内の女たち(5)【地霊の生みし人々(26)】[エッセイ]
彗星のように文壇にとび出した島田清次郎は、肥大した自己愛と傲岸不遜な言動から多くの敵をつくり、ついには社会からすらも放逐される。やがて早発性痴呆症として診断され入院、肺結核をも併発し、1930(昭和5)年、西巣鴨庚申塚の保養院で死を迎える。時に31歳。短い人生は、彼が残した小説に負けないほど波乱に満ちたものであった。
島田の1歳年上の横光利一は、既に入院生活を送る文壇の敗者に共感的な一文を、同人雑誌「文藝時代」に寄せている。「島田清次郎、今や精神病院で大胡坐をかく。恐るべし、天才、清次郎・彼、今に何をし出すか見ものである」。その期待に応えなかった清次郎の没後4年、横光は新しい才能の出現に喝采を送る。その人、森 敦の妻も庄内の女であった。
森 敦とその妻
前田 暘は1918(大正7)年1月1日、山形県飽海郡北俣村(現・酒田市)に生まれた。生家は村の代々の肝煎を務める屈指の名家で、祖父前田玄吾は初代村長を、曾祖父である仲治は県会議員を歴任した。横光利一の妻の父も県会議員であったように、文士の持つ独特の匂いに魅かれる女性の出自には共通するものがある。極貧の環境からは、負の可能性を秘めた男に掛ける余裕など生まれないのかもしれない。
前田家の養嗣子であった玄吾は、娘、よしに自分の末弟の金吾を婿とし、その間に生まれたのが暘である。学歴を積んだ金吾に家督を継がせるのは難しいと考えた玄吾は、孫で暘の長兄である元を当主とした。暘の父、金吾は、京都帝国大学英文科を1916(大正5)年に卒業し、その後もケンブリッジ大学で学んだ秀才であった。華麗な学歴に比し、金吾とよしの生活を記録したものは乏しい。したがって、時はいきなり暘が森 敦と初めて出会った1935(昭和10)年へと飛ぶ。金吾が47歳で早世して2年を経たその頃、よしは奈良市の天満町に住み、娘3人を奈良女高師附属高女(現在の奈良女子大学附属中等教育学校の前身)に通わせていた。
当時の森 敦といえば、旧制第一高等学校を退学した後、1934(昭和9)年、22歳で処女作『酩酊船』を発表し、横光利一に認められて間もない頃である。執筆場所として森が寄寓した奈良東大寺の塔頭・勧進所に、前田よしとその娘暘がたびたび訪れていたことをきっかけに互いが知り合い、心魅かれるようになる。やがて森 敦と暘は結婚の約束をするまでになるのだが、この頃には森の「十年働いて、十年好きなことをする」という生活スタイルが、既に生まれていた。
叔母から受けた住宅購入資金4000円をもとに、森はおよそ3年にも及ぶ放浪の旅に出る。蟹工船、捕鯨船、鰹や鮪の漁船に乗って漁師の群れに加わって暮らし、樺太の北限シスカに渡って厳冬のタライカ平野を彷徨したりする。
叔母の説得に従った森は、ようやく前田一家の滞在先である酒田に向かった。このときが森の庄内への第一歩で、日本海の夕焼けの素晴らしさ、月山、鳥海山の神秘的な美しさに魅せられた。暘の母の「美しいね。いつまでも信じていますよ」のひとことが、敦に結婚と就職を決意させる。デラシネ(根無し草)として生きた森だが、このときから庄内こそが唯一無二の魂のふるさととなった。
1941(昭和16)年5月、横光利一夫妻の媒酌で、前田 暘は晴れて森 敦の妻となる。目黒の雅叙園での式は盛大なものとなり、新婚旅行は社主・菊池 寛のきもいりで文藝春秋社が熱海に一流ホテルを手配してくれた。敦29歳、暘22歳であった。
残り1,195文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する