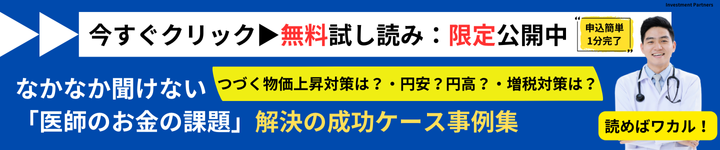お知らせ
泉 鏡花の『海城発電』─発達障害者と赤十字精神[エッセイ]
1896(明治29)年に発表された泉 鏡花の『海城発電』(岩波書店刊)は、日清戦争の最中、「赤十字の義務を完して、敵より感謝状を送られた」看護員を主人公とする物語であるが、この物語の主人公には、ある種の発達障害を思わせる特徴がみられる。(以下の引用では、読みやすさに配慮して、原文の一部を現代表記に改めた)
この作品は、神崎という赤十字の看護員が、大勢の軍人たちに取り囲まれる場面で始まる。神崎はこのとき、清国の捕虜となったときの行動を、軍人たちから詰問されていたのである。
神崎はまず、捕虜になったときにひどい拷問を受けたため、味方の内情を白状しようと思ったと正直なところを打ち明けるが、それを聞いた百人長は、「何!白状をしようと思ったか!」と、言葉を荒げる。神崎は、敵から受けた拷問の苦しさに触れて、「余り拷問が厳しいので、自分もつい苦しくって堪りませんから、すっかり白状をして、早くその苦痛を助りたいと思いました」、「実に苦しくって堪らなかったですけれども、知らないのが真実だからいえません」と付け加えたので、百人長は「知ってれば味方の内情を、残らず饒舌ッちまう処だったな」と言ったが、神崎は、親友に身の上話をするかのごとき平然たる様子で、「いかにも。拷問が酷かったです」と答えた。
すると百人長は、憤然として、「撲られた位で痛いというて、味方の内情を白状しようとする腰抜が何処にあるか」と、睨みつけた。それでも神崎は、落ち着いた様子で、「自分は何も敵に捕えられた時、軍隊の事情をいっては不可ぬ、拷問を堅忍して、秘密を守れという、訓令を請けた事もなく、それを誓った覚えもないです」と、自分はあくまでも赤十字の看護員として規則通りのことをしたまでだと言い張ったため、そこにいた軍人たちの間に、不穏の気配が漂った。
そこで百人長は、神崎を警めるような口ぶりで、「知ってれば白状したものをなんのッて、面と向ってわれわれにいわれた道理か?」と、その無責任ぶりをなじるのだが、神崎は、「無責任?左様ですか」と少しも意に介する様子がない。
百人長はさらに、「君には国家という観念がないのか。痛いめを見るがつらいから、敵に白状をしようと思う。その精神が解らない」と、太い仕込杖を手にして、2カ月間敵兵の看護をしたのだから、せめてその間に目撃した敵軍の状況を知らせろと迫ったが、それに対しても神崎は、「全く、聞いたのは呻吟声ばかりで、見たのは繃帯ばかりです」と答えるのみである。
そのため百人長は、「無神経極まるじゃあないか。敵情を探るためには斥候や、探偵が苦心に苦心を重ねてからに、命がけで目的を達しようとして、十に八、九は失敗るのだ。それに最も安全な、最も便利な地位にあって、まるでうっちゃッて、や、聞こうとも思わない」と、ため息をついたが、現在自分がいかに危険な状況にあるかに気づいていない神崎は、無邪気に「すべてこれが事実であるのです」と答えるだけだった。
残り1,360文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する