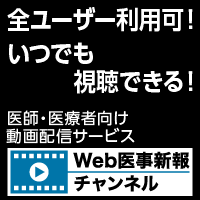お知らせ
【識者の眼】「高齢者救急医療のジレンマ」島田和幸
No.5121 (2022年06月18日発行) P.62
島田和幸 (地方独立行政法人新小山市民病院理事長・病院長)
登録日: 2022-05-30
最終更新日: 2022-05-30
- コーナー: OPINION
- 医療界を読み解く[識者の眼]
私が勤務する300床の地域中核総合病院では、毎週平均80名ほどの救急患者が搬送されてくる。年齢分布の山は明らかに70歳以上にあり、80〜90歳がピークとなることもしばしばである。背景に既に多くの疾患を持ち、急性期の症状は1〜2週間で軽快するが、すんなり自宅に帰れる人は少なく、認知症・せん妄ハイリスクケア加算や入退院支援加算など、チーム医療の対象となる人たちがほとんどである。院内死亡率や再入院率も高い。
多くの場合、本人あるいは家族は、寿命を覚悟して、主治医がDNARのことを説明すると「苦しまない方法」を希望する。すなわち、命の長さよりもQOLのほうを選ぶ。急性期病院の本来の対象は、生存期間を維持することを前提にしたevidence based medicine(EBM)を基本方針としている。たとえば、心不全治療は死亡率の減少を根拠にしたガイドラインに沿っている。したがって、終末期高齢患者は、EBMを実践している急性期病院とはミスマッチである。病院の機能分化という観点からは、急性期一般入院料1(7:1)を算定する高コストの病院ではなく、より低コストの地域包括ケア病棟や慢性期病院で、QOLをターゲットにして軸足を“ケア”においたほうが医療経済的にも理に適っている。実際、今回の診療報酬改定もその方向へ誘導しているようにみえる。
理屈はそうであっても、現場の現実は異なる。現在、在宅や介護系施設で発熱や酸素飽和度の低下、意識障害をきたし、昼夜を問わず救急搬送を要請する高齢患者は引きも切らない。1日に10人の救急患者に対応できる医療施設は、医師及び看護師数がそれなりに配置されている7:1急性期病院くらいしかなく、結局は収容先として振り出しに戻る可能性が高い。しかも患者・家族の意とは微妙にずれた“過剰なEBM医療”が提供されることになる。高齢者救急医療には、このようなジレンマが存在している。
島田和幸(地方独立行政法人新小山市民病院理事長・病院長)[高齢者][救急医療][急性期病院]