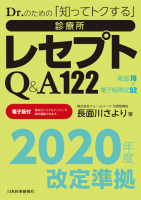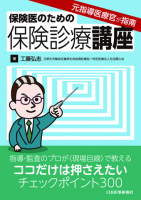お知らせ
【識者の眼】「高額療養費制度の見直しとバイオシミラー」武藤正樹
No.5285 (2025年08月09日発行) P.62
武藤正樹 (社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院グループ理事)
登録日: 2025-06-19
最終更新日: 2025-06-13
2025年3月、高額療養費制度の見直し案が患者会や与野党の反対で見送りになった。見直し案とは、収入区分の細分化や、自己負担上限額の引き上げ、多数回該当の上限額の引き上げ、である。
がんや慢性関節リウマチなどの難病の治療には、今やバイオ医薬品が欠かせない。しかし、バイオ医薬品の薬価は高額である。このため、経済的な事情を心配せずにバイオ医薬品を使用できる高額療養費制度は福音だ。

バイオ医薬品の特許が切れた後に出てくるのがバイオシミラーだ。これは、低分子医薬品におけるジェネリック医薬品のようなものであり、薬価は先行バイオ医薬品の50〜70%と安価であるため、医療費削減効果への期待が高まっている。
ただ、今回見送りになった高額療養費制度とバイオシミラーとの関係を見ると、話はちょっと複雑だ。バイオシミラーを使えば、自己負担分も先行バイオ医薬品より下がるかと言うと、そうでもない。と言うのは、先行バイオ医薬品の薬価が高いため、高額療養費制度の適応になることが多いからだ。
しかし、安価なバイオシミラーを使うと、高額療養費制度の適応にならないことがある。先行バイオ医薬品だと、自己負担分が8万円程度に抑えられるところ、バイオシミラーだと高額療養費制度の適応にならず、それより高くなってしまうことが起きる。こうした現象をバイオシミラーによる「逆転現象」と言う。逆転現象の頻度はおよそ8%もあり、医師が患者の自己負担を考えて、あえて先行バイオ医薬品を使うこともある。今回のような高額療養費制度の自己負担上限額の引き上げで、さらに逆転現象の頻度が上昇してしまうのではないかという懸念がある。
バイオシミラーによる年間の医療費削減額は1300億円にも上るとされ、バイオシミラーの普及が必須だ。しかし、高額療養費制度の自己負担上限額が引き上げられると、その普及の足を引っ張ってしまう。制度の見直しも必要だが、バイオシミラーの普及も必要である。こちらを立てれば、あちらが立たずのジレンマだ。この解決策はどうしたらよいのだろう。
それには、ジェネリック医薬品で行った、先発品への選定療養費を使うことだ。選定療養費は、ジェネリック医薬品があるにもかかわらず、あえて先発品を使う場合に、その差額の4分の1を選定療養費として、先発品の自己負担分に上乗せするものだ。この制度が2024年10月にスタートしてから、先発品の自己負担分が増えたこともあり、ジェネリック医薬品への置き換えが急スピードで進んだ。この制度をバイオシミラーにも適応し、先行バイオ医薬品とバイオシミラーの差額の4分の1を先行バイオ医薬品の自己負担分に上乗せする。上乗せ分が多額になることで、バイオシミラーによる高額療養費制度の逆転現象が抑えられ、バイオシミラーがより使われるようになる。
次回、高額療養費制度の再見直し案の国会再提出にあたっては、先行バイオ医薬品への選定療養制度と一緒に抱き合わせて法案化してほしいものだ。
武藤正樹(社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院グループ理事)[高額療養費制度][バイオシミラー][選定療養費]