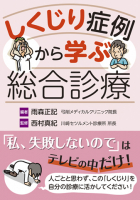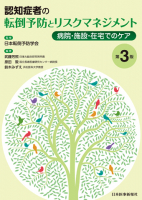お知らせ
【識者の眼】「検体取り違えを防ぐには」榎木英介
去る2024年3月26日、大阪大学医学部附属病院は、「病理診断用の検体取違いの発生について」というお知らせを公表した。
これによれば、ある患者の針生検検体が、別の患者のものと取り違えられたというものだ。調査の結果、どの段階で取り違えられたのかわからなかったという。検体取り違えにより手術が行われたため、患者に害があったということだ。

ネット上では阪大病院を批判する言葉が飛び交ったが、これは何も阪大病院に限ったことではない。全国各地の病院で、病理検体の取り違え事例が発生しており、日本中の病理関係者の大きな課題となっている。
その原因は病理組織標本を作製し診断に至るまでに多数のプロセスが存在することだ。そのプロセスは10を超える。どこでも取り違えは起こるのだ。
日本病理学会も「病理検体取扱いマニュアル─病理検体取り違えを防ぐために─」を公表している。
しかし、検体取り違えをゼロにすることはむずかしい。上記マニュアルをつくった委員会の委員長が阪大の森井英一教授だったのはなんとも皮肉なことだ。
検体取り違え事例の発生を防ぐためには、だれかを責めるのではなく、再発防止のための調査をすることが不可欠になる。これは医療事故、航空機事故などに共通して言えることである。
病理部門は病院内では比較的立場が弱いとされることも多いが、立場を超えて、だれかを責めるのでもなく、医療安全のために公正な調査ができるか、そしてそれを次の取り違え事故を防ぐ教訓とできるかが問われている。
榎木英介(一般社団法人科学・政策と社会研究室代表理事)[医療事故防止][病理組織標本]