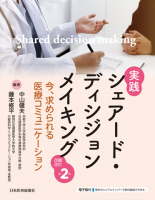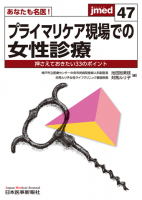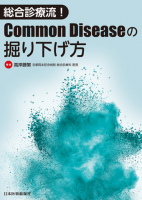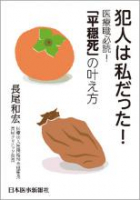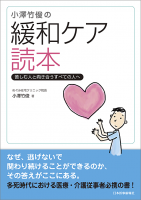お知らせ
【識者の眼】「オープンサイエンスを巡って⑧─研究公正と再現性確保のための論文のオープンアクセス」船守美穂
論文のOA化は、研究公正や研究再現性の確保のためにも進められている。研究の透明性を抑止力に使うという考え方である。
実際、研究のねつ造・改ざん・盗用などの研究不正は、本来あってはならないことではあるが、残念ながら後を絶たない。近年、任期付き雇用が当たり前となり、「優れた研究成果の継続的な輩出」が研究者キャリアの継続に必須となった。そのプレッシャーから、そうした気の迷いが起きると言われている。また、組織ベースでも同様に、時限研究プロジェクトの継続プレッシャーから、研究主幹が時に、度を超えた要求をメンバーに対して行う。
アカデミアにおける「任期付き雇用」や「競争的な時限プロジェクト」は当初、研究者を競争環境において切磋琢磨させ、より優れた成果を得ることを目的に導入された。しかし、これらの倍率が高すぎて、優れた研究者がフツーに「優れた業績」を継続的に輩出するだけでは、雇用やプロジェクトの継続に足りない場合が多すぎる。そのため、「研究不正」という、当初目的としていたものとは逆の効果が起きている。「健全な競争的研究環境」の形成を狙うのであれば、高等教育や学術に対して、もう少し余裕のある予算の組み立てが必要である。
ちなみに、「論文の取り下げランキング(Retraction Watch Leaderboard)」では、ベスト10に日本人研究者が5名も含まれるという不名誉な事態が発生している(2025年8月現在)。日本のアカデミアの競争的環境が、世界のそれより厳しいとは思えないが、早急な対処が必要である。
さて、研究不正/公正と並んでしばしば言及されるのが、「研究再現性の確保」である。両者は類似しているようで、根本的なところで異なる。研究不正は意図的に行われるのに対して、「再現性のない研究」は必ずしも意図されたものではない。研究者自身は、正確に実施した研究の成果を発表したと思っている。にもかかわらず、自身あるいは他の研究者が当該研究を追証しようとしたら、再現できない場合があり、それを「再現性のない研究」と言う。
2016年にネイチャー誌が1500名の研究者を対象に行った調査によると、他の研究者の研究を再現できなかった経験のある研究者が7割以上、自身の研究について同様の経験のある研究者が5割以上いたとされる。研究が再現できなかったとしても、当該研究が発表された論文が即座に全否定される訳ではない。しかし、他者の再検証可能性をもって、学問が積み重ね可能となることから、再現性が低いのはやはり問題である。研究の再現性の低さについても、研究不正同様、研究業績輩出プレッシャーによって、研究の成果が検証不十分となっていることが指摘されており、論文のOA化に期待がもたれている。
なお、スタンフォード大学Ioannidis教授は2006年、論文「なぜ、(医学分野の)論文のほとんどが間違っているか(Why Most Published Research Findings Are False)」を発表し、統計的に妥当な研究結果であっても、サンプルデータ数等の問題により、同結果が実際には誤っている可能性を数学的に証明した。こうした研究の再現性に関する本質的な指摘に対しては、論文のOA化以上の本腰を入れた対応が、今後必要とされる。
船守美穂(国立情報学研究所情報社会相関研究系准教授、鹿児島大学附属図書館オープンサイエンス研究開発部門特任教授〔クロアポ〕)[論文のOA化][研究透明性][研究不正][研究再現性]