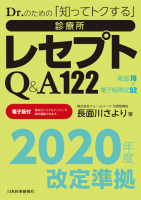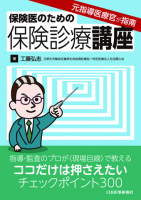お知らせ
特別企画【識者の眼】2024年度診療報酬改定をどう評価するかーその意義と課題
No.5223 (2024年06月01日発行) P.35
長島公之 (日本医師会常任理事)
松本真人 (健康保険組合連合会理事)
松田晋哉 (産業医科大学医学部公衆衛生学教室教授)
江頭芳樹 (日本臨床内科医会副会長、福岡県内科医会会長)
鈴木邦彦 (茨城県医師会長、医療法人博仁会志村大宮病院理事長・院長)
島 弘志 (日本病院会副会長、社会医療法人天神会総病院長)
橋本康子 (日本慢性期医療協会会長、千里リハビリテーション病院理事長)
仲井培雄 (地域包括ケア病棟協会会長、医療法人社団和楽仁芳珠記念病院理事長)
登録日: 2024-05-29
最終更新日: 2024-05-28
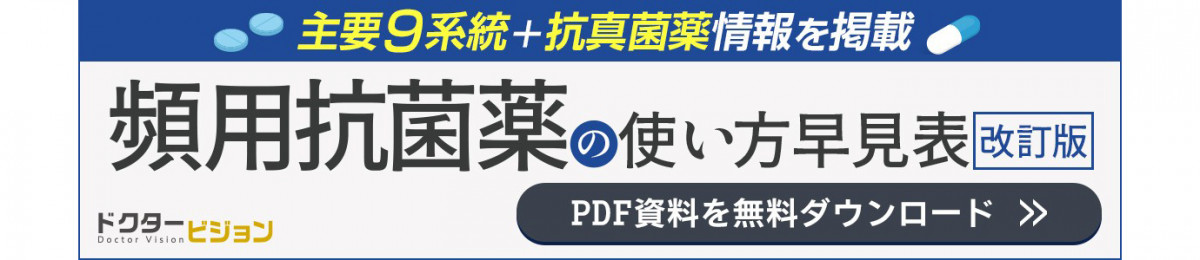
2024年度診療報酬改定が6月1日から施行される。2月14日の中医協答申から3カ月半、これまでに関係告示・通知や疑義解釈が順次示され、改定の全貌がほぼ明らかになった。
改定項目は多岐にわたり、それぞれが医療機関に大きな影響を与えそうである。と同時に、これからの超高齢社会、人口減少社会を見据えつつ、今回の改定が果たす役割についても社会の関心は高まった。
本誌は今回、「識者の眼」の特別企画として、2024年度診療報酬改定をどう評価するか、8名の方に論じて頂いた。いずれも改定に直接・間接に携わってきた実務者であり、この問題に精通した論客である。寄せて頂いた8編の論説を手がかりに、これからの医療の姿を探ってみたい。
●総論①〈インタビュー〉
「事前折衝で細かい配分まで決められるのは由々しき事態」長島公之
今回の改定は課題が多く、大変難しい作業だった。最大の課題は、職員の賃上げや物価高騰への対応。また6年に1度のトリプル改定で今後10年の医療をかたどること。さらに医療DX、働き方改革、コロナ禍を経た新しい感染症対策など、難しい課題が山積していた。

日本医師会は今回の改定に当たって、安全・安心で質の高い地域医療を安定的に継続して提供すること─を基本姿勢にして臨んだ。そこで非常に危機感を持ったのが昨年末の財政審建議だ。診療所を狙い撃ちにした形で「初・再診料を中心に診療単価の5.5%引き下げ」を打ち出してきた。これは医療費全体の△1%に相当するもので、きわめて危険な状況だった。各都道府県医師会を通じて国会議員に理解を得て頂いたこと、日医も他の団体と協力して行動したことが実を結び、△1%から本体+0.88%に押し戻すことができた。
ただ、最近は改定率を決める際に、厚生労働相と財務相の事前折衝で細かい配分まで決められるようになってしまい、大変由々しき事態だと思っている。これを変えるのは医政。「医政なくして医療なし」であり、来年の参院選もきわめて重要だと思っている。
改定の議論がデータありきで進められすぎるのも問題だ。特に最近は、平均値がカットオフの形で使われるようになっていることに危機感を持っている。診療報酬には多角的、多面的な検討が必要であり、医療現場の実感を反映させることが重要だ。
■医療DX関連は評価、入院は現場の負担への影響について検証が必要
職員の賃上げを担保するため、ベースアップ評価料が新設された。これは医療界が一丸となって要望して創設されたものなので、できるだけ多くの医療機関で活用して、人材確保につなげて頂きたい。一方、今年の春闘などをみると、今回の点数が必ずしも満足できるものではないという意見があるのも理解できる。ベースアップ評価料の対象にならない職種もあり、そこに手当てすると医療機関の持ち出しになる問題も承知している。「仕組みがわかりにくい」という声も聞いている。この点は厚生労働省に繰り返し「わかりやすい説明を」と要望している。また賃上げは本来、医療機関の状況が様々であることから、各医療機関の裁量で対応できることが理想だ。初診料、再診料、入院基本料など基本的な点数をしっかり底上げすることが今後の非常に大きな課題であると認識している。
今回の改定で評価できるのは医療DX関連。医療DX推進体制整備加算として8点(初診時)がついた。経過措置後には、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの整備などが算定要件とされたが、これらを要件とした以上、国はしっかりと環境整備をすべきだ。すべての医療機関で、できるだけ負担が少なく導入できるよう要望していきたい。今回、医療情報閲覧機能が急性期充実体制加算の要件となったが、これも多くの医療機関で負担なく導入できるよう、国が環境整備をすべきだ。在宅医療では、様々な職種が情報共有するためのICTの活用が評価された点を評価したい。
外来について、大臣折衝で生活習慣病管理料の再編が事前に決まってしまった。本来これは中医協で議論すべきで、そこは非常に遺憾だ。一方、患者の立場からすると、生活習慣病管理料(Ⅱ)が新設されたので、これを活用して患者の利益に結びつけていくことも重要ではないかと思っている。
入院では、急性期の入院料の施設基準が非常に厳しくなった。中医協で私は、「地域医療を低空飛行で必死で支えている医療機関に、これ以上重荷を負わせたら墜落してしまう」と訴えた。もはや病院に余裕はない。平均在院日数を1日でも短縮したり、項目を1つ変えたりするだけで厳しい影響が出る。これは療養病棟についても言える。医療区分の見直しなどで細分化が行われたが、現場の負担がきわめて大きくなるのではないか。6月の施行後、その影響をしっかりみる必要がある。地域包括医療病棟の目的、意義にはまったく異論はないが、各地域の医療提供体制やニーズは様々で、病院が対応できるのかという問題もある。今回の点数や要件が適切なのか、今後の検証が非常に重要だ。(聞き手:本誌・原藤健紀)
長島公之(日本医師会常任理事)
●総論②
「真の効率化、適正化で国民皆保険を維持」松本真人
まず2024年度診療報酬改定について、中央社会保険医療協議会(以下、「中医協」)の支払側委員として議論に関わらせて頂いたが、本稿は個人の認識を述べるものであり、健康保険組合連合会および中医協委員としての見解ではないことを冒頭にお断りしておく。
診療報酬自体は医療サービスの対価であるとの考えから、24年度改定では医療の質とコストに見合った評価を追求した。患者の状態と医療資源の投入量に応じた入院料の精緻化、宿日直医によるICUの評価区分の新設、生活習慣病の効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取り組みを推進するための評価体系の整理・見直しが代表的な例である。
一方で、喫緊の課題として、医療従事者の賃上げを基本料の引き上げや「ベースアップ評価料」の新設によって担保する。これまで他産業で賃金が低迷する中で、診療報酬本体は基本的に引き上げが続き、医療費の自然増も考慮すれば、まずは経営者のマネジメントによる配分の見直しによって原資を賄うことが本来の姿だと考える。ただし、政府による改定率の決定において、診療報酬本体はプラス0.88%の引き上げとなり、その大宗を賃上げに充当する財源の枠が設定された。そのため、各医療機関には確実な賃上げが求められる。
また、今回は複数の医療ニーズを併せ持つ高齢者の救急搬送を課題として重視し、その解決策として「地域包括医療病棟」や「救急患者連携搬送料」を新設することになった。経営上の判断のみならず、住民の医療ニーズを汲み取って機能を選択し、地域医療の最適化に資することを切に願うものである。
このほかにも、オンライン資格確認に加えて電子処方箋の活用や電子カルテ情報の共有を促進するための「医療DX推進体制整備加算」の新設、医師の働き方改革を推進するために「地域医療体制確保加算」の継続、さらには後発医薬品とバイオ後続品の普及策としての各種の加算の充実・新設等がある。こうした加算には実績要件を設けてコストを補償するという一定の妥当性はあるものの、診療報酬によって医療機関の取り組みを誘導する側面が強い。医療の質の向上と効率化が両立できるよう、患者への影響を含めて実態を把握し、目的通りの成果が出なければ、早急に修正すべきと考える。
また、今回は介護報酬との同時改定ということもあり、コロナ禍の経験をふまえた、地域における協力医療機関に関する体制整備の推進も含めた、医療機関と介護保険施設等との連携の強化等も盛り込まれた。
少子高齢化の進展、生産年齢人口の急激な減少、そして医療の高度化に伴い、医療保険財政、医療資源ともに逼迫した状態にあり、この状況は当分続くことが予想される。国民皆保険制度を維持するためにも、“真の”効率化・適正化が求められる。
松本真人(健康保険組合連合会理事)
●総論③
「医療と介護、障害者の連携に目配りがされた点を評価」松田晋哉
2024年度の診療報酬改定は介護保険および障害者福祉との同時改定であった。診療報酬本体の改定率は+0.88%とかろうじてプラス改定になったが、人件費や光熱費、各種材料費等の上昇を吸収しきれるものではなく、医療機関にとっては厳しい改定になった。しかし、介護報酬の改定経験がある責任者の指揮下に、今後、厚生労働省として高齢社会に対応するための方向性を明確にした改定になったことは評価できる。特に、医療と介護との連携に関して目配りが行われた点を筆者は評価している。
また、高齢化の進行に伴う医療と介護のニーズの複合化は、障害者においても同様である。その意味で障害者支援施設に入所する末期悪性腫瘍患者に対する訪問診療や医療的ケア児(者)に対する入院前支援を医療保険で評価するようにしたことは、普遍的な地域包括ケアシステム構築の重要な一歩であると考える。さらに、診療報酬、介護報酬の両方で、リハビリテーション、栄養、口腔の連携がより評価されるようになったことも、複合ニーズを持った高齢患者の増加への対応として適切である。
■入院医療─地域性を考慮した対応を
入院医療に関しては医療機能に応じた入院医療の評価の方針が掲げられ、重症度、医療・看護必要度および在院日数の見直しによる7:1看護体制の絞り込みが行われた。がん、救急、手術を急性期医療の基本とした上で、今後、各地域でその対応が課題となる高齢者救急や介護施設の医療支援、在宅ケアの支援を行う病院群の整備を、上記基準から外れる一般病床で行っていく方針が示されている。その中核となるのが地域包括医療病棟である。
DPC対象病院については、大学病院の医師派遣機能が評価されることになった。従来、医局が持っていた医師派遣機能を診療報酬で評価することで医師偏在に対応しようというものである。ただし、これについては専門医制度との整合性が今後課題となるだろう。DPC制度については、対象患者数による基準が導入された。診療密度の薄い病院を対象外にしようという意図だと考えられるが、地方によっては急性期医療を担っているにもかかわらず、診療圏における人口減のために対象外となる施設が出てくる可能性がある。地域医療支援病院の認可においても、紹介率・逆紹介率の問題で機能が公平に評価されていない事例がある。地域性を考慮した見直しが必要であると筆者は考えている。
■外来医療─次回以降、かかりつけ医機能がさらに評価へ
外来については、財務省等からの厳しい評価もあり、特定疾患療養管理料の対象疾患が見直された。この影響は大きいが、他方で地域包括診療料・加算においてかかりつけ医とケアマネジャーとの連携を評価するなど、かかりつけ医機能の評価を重視する方針が打ち出されている。今後、外来機能報告などの結果もふまえて、かかりつけ医機能が次回以降の改定でさらに評価されていくものと予想される。
松田晋哉(産業医科大学医学部公衆衛生学教室教授)
●内科診療所
「初再診料の増点だけでは賃上げには不十分な改定」江頭芳樹
今回の診療報酬改定は本体0.88%増であり、前回を単純比較で0.45%上回った。これは自民党が2012年に政権復帰して以来最大の上げ幅であった。また2023年11月の財政制度等審議会の「秋の建議」に記載された、診療所の報酬単価は初再診料を中心に5.5%程度引き下げる、との主張を跳ね返した意義はきわめて大きかったと評価している。
しかしながら、内科診療所の立場で評価すると別の側面も見えてくる。数字を羅列するのをお許し頂きたい。改定率プラス0.88%に効率化、適正化(特定疾患療養管理料の対象疾患から高血圧、糖尿病、脂質異常症を除外)で捻出するマイナス0.25%を合わせるとプラス1.13%の財源となる。そこから賃上げ加算に0.61%、食費の見直しに0.06%を用いると、残りは0.46%になる。岸田首相の強い意向で、ここから0.28%を若手医師などの賃上げに活用すると残りは0.18%になる。内科診療所に限ると前述した効率化、適正化で捻出した0.25%を0.18%より差し引かなければならないのである。したがって内科診療所に限るとマイナス0.07%の改定となった。
このことが漏れ聞こえてきた12月下旬から1月にかけて、全国の内科医会より猛烈な抗議の声が上がった。まさに内科診療所を狙い撃ちにした改定ではないか!
時系列で述べる。1月26日に厚生労働省が中央社会保険医療協議会に示した個別改定項目案で、特定疾患療養管理料の対象疾患から上記3疾患を除外する一方、これらの疾患を主病とする患者に対し同意を得て治療計画を策定し、総合的な治療管理を行った場合新たに生活習慣病管理料(Ⅱ)333点を算定できる方向性が示された。ほかにもいくつか条件があるが、検査は出来高で算定可能となった。これでシミュレーションすると今までの月1回特定疾患療養管理料225点を算定する場合と比較して、少なくとも大きなマイナスにはならないことが明らかになった。しかし月2回の受診ではマイナスになる可能性がある。また生活習慣病管理料(Ⅰ)は3疾患とも40点アップとなり、その結果内科診療所は3大疾患の治療計画を策定して患者に説明する必要が生じたのである。このことをどう評価するかは、実際に始まる6月以降の各地区からの意見を待つしかない。
ただ中医協で診療側の長島公之委員の奮闘は評価したい。今回の改定で重要な点は診療報酬も介護報酬も連携が評価されるようになったこと、言い換えれば歯科、栄養士、保健師、介護支援専門員等との情報交換が必要になり、この傾向は今後も強まると予想される。地域包括診療料、慢性腎臓病透析予防指導管理料などである。在宅時医学総合管理料、訪問頻度の高い在宅患者訪問診療料がともにマイナス改定になった影響も注視しなければならない。
以上雑駁に述べたが内科診療所の立場では、日医の努力には敬意を表するが、初再診料の増点だけでは賃上げにはきわめて不十分な改定であったと言える。
江頭芳樹(日本臨床内科医会副会長、福岡県内科医会会長)

残り5,672文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する