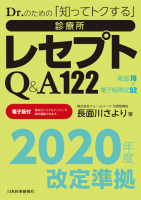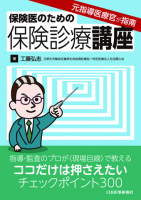お知らせ
【識者の眼】「初再診料の増点だけでは賃上げには不十分な改定」江頭芳樹
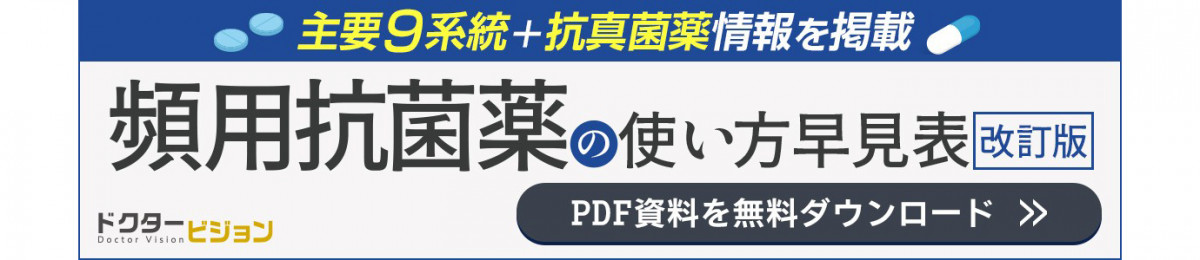
今回の診療報酬改定は本体0.88%増であり、前回を単純比較で0.45%上回った。これは自民党が2012年に政権復帰して以来最大の上げ幅であった。また2023年11月の財政制度等審議会の「秋の建議」に記載された、診療所の報酬単価は初再診料を中心に5.5%程度引き下げる、との主張を跳ね返した意義はきわめて大きかったと評価している。
しかしながら、内科診療所の立場で評価すると別の側面も見えてくる。数字を羅列するのをお許し頂きたい。改定率プラス0.88%に効率化、適正化(特定疾患療養管理料の対象疾患から高血圧、糖尿病、脂質異常症を除外)で捻出するマイナス0.25%を合わせるとプラス1.13%の財源となる。そこから賃上げ加算に0.61%、食費の見直しに0.06%を用いると、残りは0.46%になる。岸田首相の強い意向で、ここから0.28%を若手医師などの賃上げに活用すると残りは0.18%になる。内科診療所に限ると前述した効率化、適正化で捻出した0.25%を0.18%より差し引かなければならないのである。したがって内科診療所に限るとマイナス0.07%の改定となった。

このことが漏れ聞こえてきた12月下旬から1月にかけて、全国の内科医会より猛烈な抗議の声が上がった。まさに内科診療所を狙い撃ちにした改定ではないか!
時系列で述べる。1月26日に厚生労働省が中央社会保険医療協議会に示した個別改定項目案で、特定疾患療養管理料の対象疾患から上記3疾患を除外する一方、これらの疾患を主病とする患者に対し同意を得て治療計画を策定し、総合的な治療管理を行った場合新たに生活習慣病管理料(Ⅱ)333点を算定できる方向性が示された。ほかにもいくつか条件があるが、検査は出来高で算定可能となった。これでシミュレーションすると今までの月1回特定疾患療養管理料225点を算定する場合と比較して、少なくとも大きなマイナスにはならないことが明らかになった。しかし月2回の受診ではマイナスになる可能性がある。また生活習慣病管理料(Ⅰ)は3疾患とも40点アップとなり、その結果内科診療所は3大疾患の治療計画を策定して患者に説明する必要が生じたのである。このことをどう評価するかは、実際に始まる6月以降の各地区からの意見を待つしかない。
ただ中医協で診療側の長島公之委員の奮闘は評価したい。今回の改定で重要な点は診療報酬も介護報酬も連携が評価されるようになったこと、言い換えれば歯科、栄養士、保健師、介護支援専門員等との情報交換が必要になり、この傾向は今後も強まると予想される。地域包括診療料、慢性腎臓病透析予防指導管理料などである。在宅時医学総合管理料、訪問頻度の高い在宅患者訪問診療料がともにマイナス改定になった影響も注視しなければならない。
以上雑駁に述べたが内科診療所の立場では、日医の努力には敬意を表するが、初再診料の増点だけでは賃上げにはきわめて不十分な改定であったと言える。
江頭芳樹(日本臨床内科医会副会長、福岡県内科医会会長)