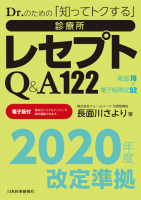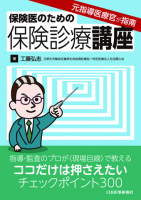お知らせ
【識者の眼】「高額療養費制度の見直し」山口育子
No.5266 (2025年03月29日発行) P.57
山口育子 (認定特定非営利活動法人ささえあい医療人権センターCOML理事長)
登録日: 2025-02-18
最終更新日: 2025-02-18
昨今、「高額療養費制度の段階的な見直し」が話題になっています。前回の見直しは2015年だったので、10年ぶりの見直しになります。
高額療養費制度はしばらくの間、自己負担分はいったん支払い、保険者の医療費の領収書を提出して、限度額を超えた分が約3カ月後に払い戻されるという償還払い制度を採用していました。それが、2007年に現物給付化し、保険者は限度額適用認定証を交付してもらい、入院時にそれを提出すると上限額しか請求されないという制度が導入されました。そして、2012年には現物給付は外来にも導入されました。

さらに、2021年10月にオンライン資格確認制度が導入されて以来、限度額適用認定証を提出しなくても、マイナンバーカードや保険証の被保険者番号によって高額療養費制度の上限額を計算する区分が医療機関に伝わるようになったのです。
このように制度が導入されてからの経緯を振り返ってみると、高額療養費制度が始まったのは1973年なので、実に53年も前から患者の経済的負担を支えてくれている制度ということになります。多くの患者にとっては、「当たり前」のサポートシステムになっているのだと思います。
しかし、本当に「当たり前」ですませてよいのでしょうか。私自身も何度も高額療養費制度の恩恵にあずかりながら、一方で疑問も抱き続けてきました。というのも、償還払い制度だった時代は、いったん負担分を全額支払っていたので、自分が使っている医療費をまだ実感できていました。ところが、現物給付になってからは、上限額しか請求されなくなり、自分がいったいどれだけの医療費を使っているのか実感が湧かなくなっているのではないかと危惧の念を抱くようになったのです。
このような「ありがたい制度」が導入されている国はほかにありません。しかし、多くの日本人にとっては、いったん「患者」になれば、なくてはならない制度になっています。ただ、いつまで財源がもつのだろうか。もし突然、「もう高額療養費制度は維持できなくなりました」と梯子を外されると、治療の継続ができなくなる人が続出する。そうなってからでは遅いという危惧の念が私の中にずっとあるのです。
高齢化と医療の高度化、高額薬剤の開発や普及によって、高額療養費の支給金額は3兆円近くに膨れ上がっています。特に、1000万円以上の高額レセプトの件数が急激に増えています。
患者側の団体からは今回の制度見直しについて反対の意見が出ています。しかし、自己負担額が上がることだけを問題視したり不満を述べたりするのではなく、この先、ますます高齢者が増え、生産年齢人口が減少していく中で、このようなセーフティネットの制度をどうするのか、真剣に考える必要があるのではないかと思うのです。
誰しも負担は少額ですませたい、では誰が負担するのか─医療を個人の視点だけでなく、社会を視野に入れて考えることが大切だと思います。
山口育子(認定特定非営利活動法人ささえあい医療人権センターCOML理事長)[高額療養費制度][高齢化][制度見直し]