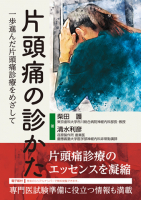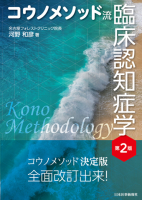お知らせ
【識者の眼】「ボツリヌス・オン・ザ・レッドリスト」目崎高広

前稿(No.5272)の予告どおり、本稿では、私の専門であるボツリヌス毒素療法と、その惨状について書きます。
米国発のこの治療は、世界中の多くの診療科で用いられています。一般的には美容のほうが有名かもしれません。基本的な作用は、運動神経終末での神経筋ブロックです(ほかにもあります)。注射による対症療法ですが、多くの疾患で劇的な効果を示します。

先進国では、ごく普通のこの治療ですが、日本では絶滅、少なくとも近未来における治療技術の大幅な劣化が、危惧されているのです。需要が多く、安全・有効な治療なのに……。
まず、治療に従事している医師(登録医師ではなく、まともな治療ができる医師)が増えません。大学によっては「学内では行わないこと」「したければ関連病院で」と指示している(いた)そうです。患者は増えるばかり、長い時間がかかり、儲からず、研究の妨げになるからと思われます。しかしこれでは、技術の伝授が成立しません。私の勤務地は三重県ですが、日帰りが難しい遠方の患者が何人もいます。それだけ従事者が少ないことを意味します。一度きりのセミナーで「できる」ようになる治療ではありません。一定期間の継続訓練が必要なのに、指導者が少ない(興味もない)、だから次世代は(興味があっても)教われない、また忙しすぎて従事できないのです。下手に手を出すと仕事が増えるだけ、だから専門家に丸投げします。これでは普及しません。先細りは構造的な問題なのです。
次に技術の拙劣です。なぜこんな、と絶句するような方法で治療を受けた患者を多く診てきました。おそらく手ずから教わらずに、見よう見まねで注射しているのでしょう。しかし「どこへ」「どれだけ」という匙加減が成否を決める治療です。例を挙げましょう。痙性斜頸での有効率は国内で均すと約5割、しかし、専門施設での有効率はおおむね70〜80%です。専門施設には、より難度の高い患者が集まると思われるにもかかわらず。この差は手技の巧拙によると思われます。
3つ目はお金の問題です。技術料は400〜9680点と、効能によって大差があります。しかし、400点の治療が簡単なのではありません! 1時間かけても終わらない患者もいます。症状に応じた工夫をすればするほど、赤字は大きくなります。注射にモニタが必要な患者も、モニタ加算がありませんから、自治体によっては算定を認めません。経営に苦しむ病院にとって、こんな治療は厄介者扱いでしょう。安すぎる診療報酬が普及を大きく妨げていることは明々白々です。
最後に効能・効果の問題を挙げます。海外では第一選択とされるのに国内で使えない疾患が多数あります。効かないほかの治療でお茶を濁すのは、医療として非効率です。何より患者を救えません。
私も長年努力しましたが、深い徒労感があります。国策として絶滅させたいのなら諦めるべきでしょうか。
目崎高広(榊原白鳳病院脳神経内科)[ボツリヌス毒素療法]