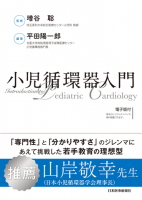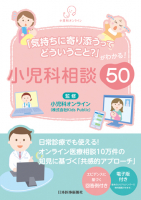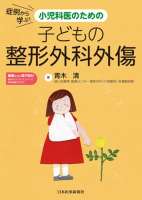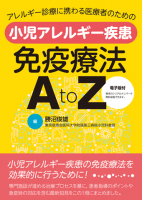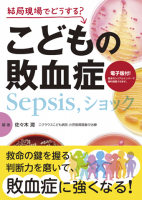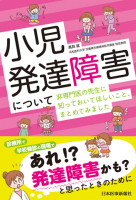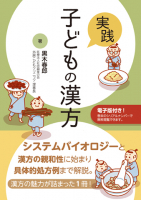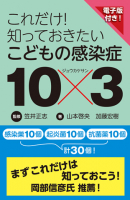お知らせ
【識者の眼】「新生児医療の歴史と社会的インフラとしてのNICU医療」豊島勝昭
私は、小児病院の新生児集中治療室(NICU)で28年間勤務してきました。人工呼吸器や保育器に囲まれた空間で、心エコー検査に基づいた循環管理を行い、早産児・低出生体重児・様々な疾患とともに生まれた新生児の後遺症少なき救命をめざしてきました。NICUの応援者やNICUで働くことを志す後輩が増えたらと願って、地域の小中高校や看護学校で『いのちの授業』を17年間で130回以上担当し、テレビドラマ『コウノドリ』を監修しました。
早産や低体重で生まれた赤ちゃんの命を救いたいと願った産科医や小児科医が、日本で初めて1000gの新生児を救命することができたのは、今から約100年前のことです。日本新生児医学会が1965年に設立され、全国的にNICUの整備が進みました。日本から早産児の肺機能を高める人工サーファクタントが開発されて救命率が飛躍的に向上し、NICUがない病院で生まれた早産児でもNICUのある病院に搬送して治療を受けられる連携体制ができました。1986年に厚生労働省の支援によって、NICU施設基準の設定やNICU加算が診療報酬制度に組み込まれました。現在、日本の新生児の約30人に1人が、NICUで何らかの医療を受けています。医療・行政の関係者の協働で、NICUが社会的インフラとなって50年、日本は救命率がきわめて高い新生児医療体制を構築しています。

NICUで担当した子どもたちが成長して、小児病院に入職してくれることも増えてきました。NICUで救われた命が、地域で育ち、命を救い支える側になりたいと戻ってきてくれる姿に、NICUは命の循環を支える“社会的インフラ”と実感します。
全国の自治体で、小児医療無償化が進んでいることは喜ばしいことです。一方で、小児病院であっても、生命維持装置である閉鎖型保育器や人工呼吸器、超音波検査装置の更新が難しく、クラウドファンディングに頼らざるをえない状況になりつつあります。命を救う医療機器の整備がままならない現状は、医療安全に直結する重大な課題です。新生児医療は、警察署や消防署と同じく、収益ではなく“社会的インフラ”ととらえる視点が求められると考えます。
NICUは昼夜や休日を越えて生まれる赤ちゃんの救命医療を常に維持することに加えて、授乳や育児、発育支援が求められます。集中治療のスキルと育児支援、家族応援のマインドのあるスタッフの育成には、時間と労力が必要です。人員増がないままに働き方改革を推進することは、NICUでスタッフ育成の困難さや赤ちゃんの療養環境の質の低下が危惧されます。また、病院経営の効率化によって、NICUの医療機器整備や人財育成の費用が過度に抑えられ、後遺症少なく救えるはずの命を救えなくなるのではないかと危惧しています。財政難の中でも、各地域のNICU医療体制の課題に対応する政策を、医療・行政の関係者で協力して考えていく必要があります。
少子化の時代だからこそ、生まれてくる命を手厚く支える体制の維持と向上が求められています。誰かの命の始まりが、また誰かを支える力になる─その連鎖を守るためにも、新生児医療を〈日本の未来を支える場所〉のひとつとして、社会全体で見守って頂けたらと願っています。
豊島勝昭(神奈川県立こども医療センター新生児科部長)[新生児医療][NICU]