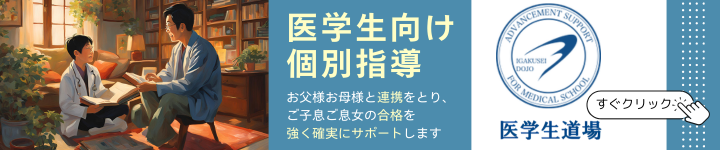お知らせ
「死についての授業」をはじめたワケ[炉辺閑話]
医師になる人たちのモチベーションは、「人を助ける」ということが根本にあることは言うまでもないことだろう。私自身も「人を助ける」ということで医学部を選んだし、実際それを目的に医療をやってきた。しかし、その一方では、我々は多くの患者「助けられない人」の死にも直面する。私にとって、それは、医学部入学当時、まったく認識していなかった医師の仕事の一面であった。実際、医学部のカリキュラムの中には人の死を診る、あるいは、看取るということが含まれておらず、医師となって初めて人の死を体験することがほとんどだ。私も研修医になって初めて死を看取る場面に立ち会った。がん終末期の患者さんに死の宣告をしたところ、上級医がやってきてまだ頸動脈の脈波が触知できることがわかり、家族の前で恥ずかしい思いをした経験がある。
以前より、医師が死に接する機会が最も多い職業のひとつであるにもかかわらず、患者個人の一生を締めくくる大イベントである「死」に対する医師の姿勢や心構えについて、指導や教育はもちろん、意見を交換したり共有したりする機会が少なすぎると感じていた。特に私は消化器外科が専門であったこともあり、がん患者さんの終末期に接することが多かった。自分の受け持った患者さんについては、それなりに対応してきたつもりではあるものの、その対応でよかったのか、あるいは十分なことができたのか、など常々疑問を感じていたし、死への対応が各医師個人の裁量で行われ情報が共有されていないことに違和感を持っていた。医師として、プロフェッショナルとして、患者あるいは人の死についてとらえる必要があるのではと思ってきたことが、「死についての授業」を始めたきっかけである。

4年前(2017年)より、医学部2年生の学生さん(20歳前後)を対象に、年末の丸1日を授業に当ててもらっている。午前中、事前に学生に対して行った死についてのアンケート調査の結果を発表し、座学の授業を行い、午後からは、7人ずつのグループにわかれて9~10の各課題について2班ずつが討議し発表してもらうワークショップを行っており、1日がかりのプログラムである。
これまでのアンケート結果(2017~19年)で驚いたのは、自分の死に対して認識している人が全体の34~48%と以外に少ないことであった。自分の死を意識せずに患者の死に向きあえるのか、など素朴な疑問が湧いてくる。自分の死を意識した人の中の33~59%、身近な人の死を経験した人の20~24%に生活の変化が起こっており、その中に、医学部進学を決意したことが含まれていたことは興味深い(3~8人/年)。座学では、死亡診断の方法や死亡診断書の書き方など基本的なことはもちろん、安楽死や尊厳死の日本と世界での実態とその考え方など、これまでの授業ではほとんど教えられていなかった内容を提供している。
ワークショップでは様々な課題を取り上げており、安楽死に関する課題では、アメリカで、脳腫瘍と診断されて安楽死を選んだ29歳女性ブリトニー・メイナードさんの例を挙げて、日本でも安楽死を認めるのか、否か?の問いかけをしたり、ALSに関しての課題では、日本では70%の患者が家族への負担を考えて尊厳死を選んでいることについての是非を問い、さらに、人工呼吸器をつけてから尊厳死を選びたい人をどうするのか、という問題についても考えてもらっている。
私自身は小学校2年生で死を意識したが、そのときは恐怖で1週間ほど眠れなかった。「死についての授業」が、自分たちの死の経験を共有する場を提供し、「死」について考える習慣をつけるきっかけとなれば、と願っている。