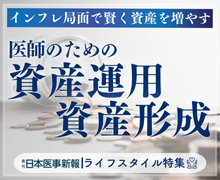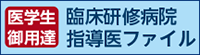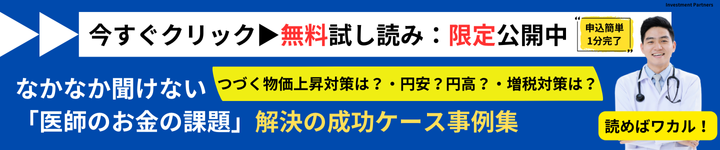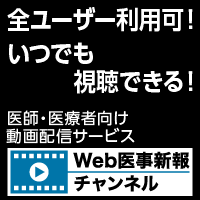お知らせ
【識者の眼】「総合診療専門医制度をめぐる新たな展開」草場鉄周
No.5144 (2022年11月26日発行) P.57
草場鉄周 (日本プライマリ・ケア連合学会理事長、医療法人北海道家庭医療学センター理事長)
登録日: 2022-10-24
最終更新日: 2022-10-24
- コーナー: OPINION
- 医療界を読み解く[識者の眼]
本年7月より日本専門医機構は新任の渡辺理事長をトップに大幅な人事の入れ替えを経て第5期目(9年目)に入った。総合診療専門医に関する協議は学会ではなく日本専門医機構で行う方針は踏襲されており、今期の総合診療専門医検討委員会は千葉大学総合診療部の生坂政臣先生が委員長としてその任を担っていくこととなった。歴代の委員長は総合診療の専門家ではなかったが、今回初めて総合診療の専門家が委員長となったことは歓迎すべきことであり、制度設計に当初より関わってきた立場からは大変嬉しく思っている。
また、私自身も第1〜3期の委員会には参加していたが、第4期は直接関わりがなかった。今回、委員としての再登板の要請があり、お引き受けすることとなった。2年を経て久しぶりに委員会に参加した印象は、事務局体制が相当整備されて制度運営も軌道に乗っているという実感であった。また、制度スタート時より抱えていた幾つかの課題についてもようやく見直しに入る環境が整ってきたこともあり、参加者の立場にこだわらず自由で率直な討議ができている点も高く評価できるだろう。
現在、議論の中心となっているのはサブスペシャルティのあり方、そしてローテーションの自由度を高める方向性の2点である。サブスペシャルティについては家庭医療、病院総合診療、地域総合診療という3領域が各学会より提示され、委員会としてはそれを支持する方向で議論しているが、肝腎の機構本体のサブスペに関する立場が揺れ動いており、決着点はまだ見えてきていない。また、ローテーションの自由度については、現在の枠組みでは自由な選択研修の枠がまったくないため、総合診療に必要な整形外科、皮膚科、産婦人科などを学ぶチャンスがないことが問題となっている。必修となっている内科研修などを調整することでその余裕がつくれるか、細かい議論が行われている。
また、総合診療専門研修を選択する専攻医は年180〜250名程度とこの4年間でほとんど伸びていないという大きな問題があり、委員会として専攻医数増大のための方策が必要という認識で一致している。総合診療領域の発展のためにもオールジャパンで汗をかいていきたい。
草場鉄周(日本プライマリ・ケア連合学会理事長、医療法人北海道家庭医療学センター理事長)[総合診療/家庭医療]