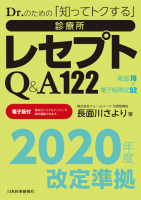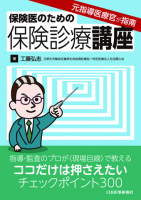お知らせ
【識者の眼】「事前折衝で細かい配分まで決められるのは由々しき事態」長島公之
今回の改定は課題が多く、大変難しい作業だった。最大の課題は、職員の賃上げや物価高騰への対応。また6年に1度のトリプル改定で今後10年の医療をかたどること。さらに医療DX、働き方改革、コロナ禍を経た新しい感染症対策など、難しい課題が山積していた。
日本医師会は今回の改定に当たって、安全・安心で質の高い地域医療を安定的に継続して提供すること─を基本姿勢にして臨んだ。そこで非常に危機感を持ったのが昨年末の財政審建議だ。診療所を狙い撃ちにした形で「初・再診料を中心に診療単価の5.5%引き下げ」を打ち出してきた。これは医療費全体の△1%に相当するもので、きわめて危険な状況だった。各都道府県医師会を通じて国会議員に理解を得て頂いたこと、日医も他の団体と協力して行動したことが実を結び、△1%から本体+0.88%に押し戻すことができた。

ただ、最近は改定率を決める際に、厚生労働相と財務相の事前折衝で細かい配分まで決められるようになってしまい、大変由々しき事態だと思っている。これを変えるのは医政。「医政なくして医療なし」であり、来年の参院選もきわめて重要だと思っている。
改定の議論がデータありきで進められすぎるのも問題だ。特に最近は、平均値がカットオフの形で使われるようになっていることに危機感を持っている。診療報酬には多角的、多面的な検討が必要であり、医療現場の実感を反映させることが重要だ。
■医療DX関連は評価、入院は現場の負担への影響について検証が必要
職員の賃上げを担保するため、ベースアップ評価料が新設された。これは医療界が一丸となって要望して創設されたものなので、できるだけ多くの医療機関で活用して、人材確保につなげて頂きたい。一方、今年の春闘などをみると、今回の点数が必ずしも満足できるものではないという意見があるのも理解できる。ベースアップ評価料の対象にならない職種もあり、そこに手当てすると医療機関の持ち出しになる問題も承知している。「仕組みがわかりにくい」という声も聞いている。この点は厚生労働省に繰り返し「わかりやすい説明を」と要望している。また賃上げは本来、医療機関の状況が様々であることから、各医療機関の裁量で対応できることが理想だ。初診料、再診料、入院基本料など基本的な点数をしっかり底上げすることが今後の非常に大きな課題であると認識している。
今回の改定で評価できるのは医療DX関連。医療DX推進体制整備加算として8点(初診時)がついた。経過措置後には、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの整備などが算定要件とされたが、これらを要件とした以上、国はしっかりと環境整備をすべきだ。すべての医療機関で、できるだけ負担が少なく導入できるよう要望していきたい。今回、医療情報閲覧機能が急性期充実体制加算の要件となったが、これも多くの医療機関で負担なく導入できるよう、国が環境整備をすべきだ。在宅医療では、様々な職種が情報共有するためのICTの活用が評価された点を評価したい。
外来について、大臣折衝で生活習慣病管理料の再編が事前に決まってしまった。本来これは中医協で議論すべきで、そこは非常に遺憾だ。一方、患者の立場からすると、生活習慣病管理料(Ⅱ)が新設されたので、これを活用して患者の利益に結びつけていくことも重要ではないかと思っている。
入院では、急性期の入院料の施設基準が非常に厳しくなった。中医協で私は、「地域医療を低空飛行で必死で支えている医療機関に、これ以上重荷を負わせたら墜落してしまう」と訴えた。もはや病院に余裕はない。平均在院日数を1日でも短縮したり、項目を1つ変えたりするだけで厳しい影響が出る。これは療養病棟についても言える。医療区分の見直しなどで細分化が行われたが、現場の負担がきわめて大きくなるのではないか。6月の施行後、その影響をしっかりみる必要がある。地域包括医療病棟の目的、意義にはまったく異論はないが、各地域の医療提供体制やニーズは様々で、病院が対応できるのかという問題もある。今回の点数や要件が適切なのか、今後の検証が非常に重要だ。(聞き手:本誌・原藤健紀)
長島公之(日本医師会常任理事)