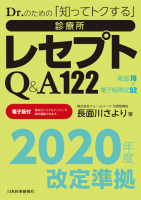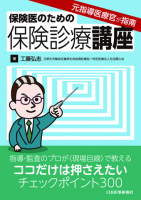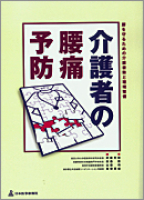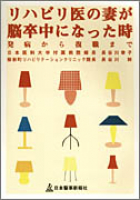お知らせ
■NEWS 一般病棟用・看護必要度における内科の不利解消で対応案を提示―厚労省
厚生労働省は9月11日の診療報酬調査専門組織入院・外来医療等の調査・評価分科会に、一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」の評価における内科系症例と外科系症例の格差是正のための対応案を提示した。救急搬送からの入院や緊急入院の大半が内科系症例であることに着目。1床当たりの救急搬送応需件数と「協力対象施設入所者入院加算」の算定回数の合計数を一定の計算式にあてはめて算出した値を該当患者割合に加算することで、内科系症例が多い病棟の該当患者割合の底上げを図る内容となっている。
一般病棟用の看護必要度を巡っては、内科系症例のA・C項目への該当割合が外科系症例に比べて低い点が課題となっている。特に救急搬送による入院や緊急入院では内科系症例の割合が約8割を占め、救急搬送で入院した内科系症例の該当患者割合は、いずれの入院料においても救急搬送ではない外科系症例に比べ、低い傾向にある。

24年度診療報酬改定時にA項目の「救急搬送後の入院/緊急に入院を必要とする状態」の評価日数を従来の5日間から2日間に短縮したことが問題発生の一因と考えられることから、評価日数を5日に戻すことも一案となり得るが、厚労省は入院日数を長引かせる誘引になりかねないと否定的。代わりにそうしたデメリットを解消できる方策として、「救急搬送応需件数(外来帰宅可となった件数も含む)を各病棟に按分した病床当たり件数」と「各病棟における『協力対象施設入所者入院加算』(介護保険施設からの緊急入院受け入れに対する評価)の病床当たり算定回数」の合計数に一定の係数を乗じて算出した値を該当患者割合に加算することで、該当患者割合を底上げする案を提示した。この案に対して委員からは賛否両論が示された。
■「急性期一般1」のB項目評価、一定期間経過後は6〜7割の患者で得点に変化なし
同日は「急性期一般入院料1」等でのB項目の取り扱いについても議論した。これらの入院料においてB項目は該当患者の基準からは外れているものの、評価は行うことになっており、病院団体は評価も不要とすることを要望している。入院後一定期間経過後は6〜7割程度の患者でB項目得点が不変となることから、委員からはこれらの患者を評価対象から除外すべきなどの提案があったが、現行の方法での評価継続を求める意見もあった。