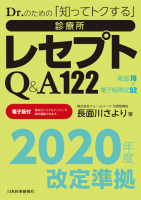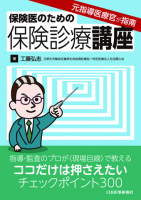お知らせ
■NEWS 入退院支援、身寄りがなく同居人不明の患者の対応が論点に―入院外来医療分科会
診療報酬調査専門組織の入院・外来医療等の調査・評価分科会は8月28日、入退院支援や高齢者の救急搬送への対応としての後方支援のあり方を巡り議論した。入退院支援については、「入退院支援加算」の算定対象とはなっていない、身寄りがなく同居人が不明の患者の取り扱いが論点となった。
厚生労働省が提示したデータによると、退院困難な患者の中で退院調整完了までに最も時間や人手を要するのは「身寄りがなく同居者が不明な者」であり、回答全体の7割以上を占める。「入退院支援加算」は退院困難な要因(算定要件)に該当した場合のみが算定可能だが、「身寄りがなく同居者が不明な者」は現行要件に含まれていない。

こうした患者の入退院支援について診療側の津留英智委員(全日本病院協会常任理事)は、「医療現場は大変困っている。現行では算定要件外だが見直しが必要だと思う」と算定要件への追加を提案した。
一方、高齢者救急への対応では、在宅療養後方支援病院や介護保険施設の協力医療機関と在宅医療提供医療機関、介護保険施設等の連携を一層強化することによって、救急搬送の増加を抑制することが求められる。
だが、介護保険施設の協力医療機関うち常時の相談、常時の診療、常時の入院体制の3要件をすべて満たす医療機関の割合は半数程度であり、特に「急性期一般入院料1」の算定病棟のみの医療機関での割合が低かった。
■「協力対象施設入所者入院加算」、算定対象医療機関の届出は約4割
また、協力医療機関による入院受け入れを評価する「協力対象施設入所者入院加算」について、算定対象医療機関である在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、地域包括ケア病棟を持つ病院の届出割合は約4割にとどまることが分かった。非届出医療機関が届出をしていない理由では、ICTによる情報共有体制の整備やカンファレンスに関する要件の充足が困難なためとの回答が多かった。
協力医療機関における入院受け入れの現状について秋山智弥委員(名古屋大学大学院医学系研究科客員教授)は、介護保険施設からの要請が増え、それ以外の緊急患者の受け入れに支障を来たしているケースもあると指摘。協力医療機関の負担軽減のためには、介護保険施設の対応力を強化し、緊急入院自体を減らすことも重要との認識を示した。