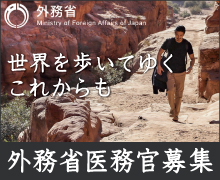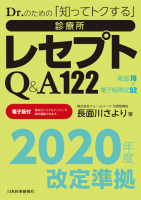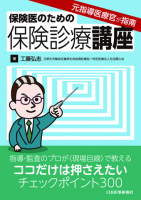お知らせ
【識者の眼】「情けは人の為ならずの社会保障論」松原由美
米国で最も注目を集めている経営学者の1人であるアダム・グラントは、組織の人間を3つのタイプに分類した1)。ギバー(他人を助け、貢献し、見返りを求めない人)、マッチャー(くれるならあげるというようにギブアンドテイクのバランスを取ろうとする人)、テイカー(自分の利益を優先する人)である。アダム・グラントが行った調査によると、この3つのタイプのうち、最も成功するタイプは、ギバーであるという。なぜならギバーは周囲から信頼、協力を得やすいからである。情けは人の為ならずが、実証されたと言えよう。短期的視点ではギバーは与えているだけで損をしているようにみえるが、長期的にみれば得をしているのだ。
岡 檀氏の長年の調査によると、長期的視点での損得勘定は自殺率低下にも有効だという2)。全国でもきわめて自殺率の低い徳島県(旧)海部町は、「生き心地の良い地域」をつくっているが、その海部町には「病、市に出せ」という教えがある。それは、病や問題は自分だけで抱えずに、早めに表に出し相談することを勧める先人の知恵である。岡氏によると、こうして周囲に助けを求めることへの心理的抵抗を軽減し、「生き心地の良い地域」づくりができている出発点は、住民の損得勘定にある。隣人が悩み、取り返しのつかない事態になれば、共倒れもありうる。早めに問題を開示させ周囲が助けることが、長い目でみれば損失を大きく減らせるという知恵と価値観が、当該地域の文化として根づいている。

社会保障は短期的には負担にみえても、長期的視点にたった損得勘定で考えれば得である。たとえば将来、いつどのような病気になるか、事故にあうかはわからない。健康的な生活、人生を送るには、必要なときに必要な医療やケアを受けられる社会保障の整備が欠かせない。また、医療等のいつ起きるかわからないリスクに対し、自己責任に頼る制度では、将来の不安から人々の過剰な貯蓄を増長し、経済がいっそう回らなくなる。保険など不要だと信じ無保険でいて、たとえば必要な医療を受けられずに障害が残る、働けなくなる、その子どもも貧困に陥る等となれば、本人の周囲、ひいては日本の財政にも影響を及ぼす。
さらに、既に日本の人口の約8人に1人が医療・福祉分野に従事している時代に、社会保障の抑制政策は、医療・福祉従事者に将来の不安を増幅させて人手不足をまねくほか、消費行動を抑制し経済を停滞させる一因となろう。
社会保障制度はギバーの制度化とも言える。社会保障は負担論ばかりが注目されるが、情けは人の為ならず。社会保障は巡り巡って経済に、雇用に、社会安寧に、自分自身に得であることの認識と、それを守り育てる視点が求められる。
【文献】
1)アダム・グラント: GIVE & TAKE「与える人」こそ成功する時代. 三笠書房, 2014.
2)岡 檀:生き心地の良い町 この自殺率の低さには理由がある. 講談社, 2013.
松原由美(早稲田大学人間科学学術院人間科学部教授)[社会保障制度][損得勘定]