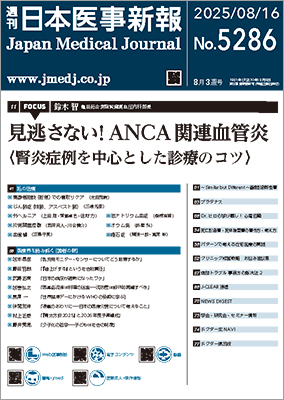お知らせ
【識者の眼】「災害医療DX:災害時モード搭載の重要性」土屋淳郎
No.5272 (2025年05月10日発行) P.61
土屋淳郎 (医療法人社団創成会土屋医院院長、全国医療介護連携ネットワーク研究会会長)
登録日: 2025-04-04
最終更新日: 2025-04-01
2025年3月8・9日に開催された日本医師会医療情報システム協議会(日医協)は、メインテーマが「災害かつ再生に役立つ医療DX」であった。筆者が委員を務める東京都医師会医療情報検討委員会の答申書でも、災害医療におけるICT利用についての検討を担当していたこともあり、非常に興味のある内容であった。答申書での内容は主に、災害のフェーズに合わせて利用するシステムが変わること、利用するシステムにはフェーズフリーという考え方と災害時モードの搭載が必要だ、という内容である。フェーズフリーについては以前の本連載(No.5209)でも書いているので、本稿では「災害モード時の搭載」について触れてみたい。
そもそも災害対策は収益を生む事業ではないし、災害があったときにしか役に立たないという側面が少なからずあるため、予算もつきにくい傾向があり、専用システムをつくるよりは、普段から使っているシステムを災害時にも利用できるようにする「災害時モードの搭載」は重要であると思われる。

日医協の発表でも、普段から地域医療連携システムとして利用している「いしかわ診療情報共有ネットワーク」において、ID-Linkの「EMS機能」を用いることで、被災者の医療情報を速やかに得ることができたのは有用との報告もあった。また、オンライン資格確認等システムの「災害時医療情報閲覧機能」(災害時モード)でも、避難した被災者の患者情報(薬剤情報・診療情報・特定健診情報、保険者番号等の資格情報など)を確認することができるとのことであった。資格確認端末が使えないなど災害時モードを利用できない際にも、患者自身のスマートフォンからマイナポータルで服薬履歴の確認も可能となっている。
しかし、まだまだ課題も多い。もちろん電気と通信のインフラが必要であるし、そもそもそれらのシステムを普段から利用し、必要な情報が入力されていないと引き出す情報もない。災害時の個人情報保護は普段と異なることを理解した上で、災害時モードの切り替えをだれがどのように行うかなども決めておかなければならないだろう。
とはいえ、東日本大震災の際に福島県の病院で被災した筆者が、病院の近くにある体育館に避難してきた人たちの病歴も内服薬もわからず、途方に暮れたときとは隔世の感がある。あれから14年、これからもさらに災害医療DXがすすみ、来たるべきときが来たときに使える仕組みになっていることを強く期待したい。
土屋淳郎(医療法人社団創成会土屋医院院長、全国医療介護連携ネットワーク研究会会長)[医療DX][災害医療]