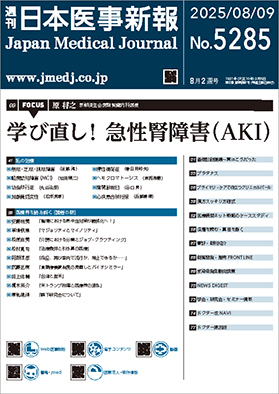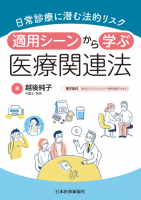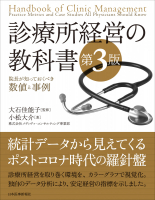お知らせ
【識者の眼】「救急搬送、いつまで無料にしているのか?」康永秀生
康永秀生 (東京大学大学院医学系研究科臨床疫学・経済学教授)
登録日: 2025-08-13
最終更新日: 2025-08-06
日本では、救急搬送は原則として無料である。一部の自治体で、「選定療養費」制度の枠組みを用いて、救急搬送患者に対して緊急性がないと医師が判断した場合、費用を徴収することができるとしている。これについて、私見を述べる。
経済学では、財・サービスを「公共財」と「私的財」に区分する。国防・警察・消防などは、純粋公共財である。市場に出回るほとんどの財・サービスは、私的財である。保健・医療サービスについては、公衆衛生や災害医療などいくつかは公共財にあたるものの、多くは私的財である。救急車による搬送がどちらにあたるかは国によって考え方が異なり、英国・日本などでは公共財、米国などでは私的財の扱いである。

公共財とは本来、非競合性と非排除性を備えていなければならない。このうち非競合性とは、ある者の消費が、他の者の消費を妨げない特性である。日本の救急搬送は、非競合性の要件を満たさなくなりつつある。救急搬送される人数は増加し続け、救急車の台数が足りず、救急要請から病院到着までの時間も延長している。ある者の救急車利用が、他の者の利用を妨げている状況である。
そうなれば、救急車は私的財と考え、有料にするのが妥当である。結果的に緊急性があろうとなかろうと、一律有料にすることが最も合理的であり、公平である。
救急搬送の対価を選定療養費制度の枠組みで徴収するのは、いくつかの点で不合理である。まず、選定療養費の主な目的は、医療機関の機能分担を推進し、国民皆保険制度を維持することにある。救急搬送の件数を少なくすることが目的ではない。
次に、緊急性の有無について現場の判断にゆだねることは、医療機関をはじめ、様々な現場の負担になり、医療従事者と患者とのトラブルの元にもなりうる。1例として、「選定療養費」制度を2024年12月に開始した茨城県において、中学校内で負傷した生徒を教員が救急要請し、実際に搬送されたところ、医療機関では緊急性がないと判断され、費用を請求されたという。
県によれば、救急電話相談で救急車を呼ぶよう助言を受けた患者からは原則費用を徴収しないことを、県と病院側が事前に申し合わせていた。このケースでは、電話相談がされていなかったという。こういったトラブルが起こってしまうのは、「この場合は有料、この場合は無料」などと選別するからである。
救急車を有料化すれば、本当に搬送が必要なケースであっても救急要請を躊躇してしまう、という懸念は昔からよく聞かれる。しかし、搬送が必要なほどの重症例ならば、たとえ搬送までは無料であっても、入院後のサービスは一律有料である。そうみれば、搬送の対価のみを無料とする根拠はさほどない。救急車は一律有料とすべきであり、搬送後に受ける医療サービスと同様、公的医療保険に組み入れることを検討すべきである。
康永秀生(東京大学大学院医学系研究科臨床疫学・経済学教授)[経済学][救急搬送][選定療養費]