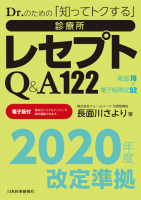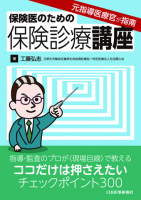お知らせ
■NEWS 特定機能病院の逆紹介率の低さが論点に―入院・外来医療分科会
診療報酬調査専門組織の入院・外来医療等の調査・評価分科会は7月17日、外来機能の分化や病院と診療所の連携について議論した。厚生労働省はこの中で、紹介外来を基本とする特定機能病院の平均逆紹介率が減算基準を下回っている現状を示したが、委員からは定期的なフォローアップが必要な悪性腫瘍患者などが含まれている可能性があるとして、より詳細な分析を求める声が相次いだ。
特定機能病院や一般病床200床以上の紹介受診外来重点医療機関などには、紹介率・逆紹介率が基準を下回る場合の減算規定が設けられている。

減算規定対象病院の外来診療の分析データをみると、特定機能病院以外の逆紹介率は中央値、平均値とも減算基準を超えるが、特定機能病院の平均値は基準を下回る。また、再診患者のうち2年以内に「初診料」の算定がない患者の割合は約6割以上、直近6カ月以内に再診を受けた患者の割合は平均8割程度だったが、いずれも特定機能病院の割合が最も高い。
特定機能病院の逆紹介率の低さなどについては複数の委員が、一般的な疾患だけでなく、外来での定期的なフォローアップが必要な悪性腫瘍患者や外来化学療法の患者が含まれる可能性を指摘。「大学病院と同様の医療を行っているDPC特定病院群の逆紹介がどの程度なのか併せて見ていく必要がある」(牧野憲一委員・旭川赤十字病院特別顧問・名誉院長)、「(逆紹介の推進を)一歩進めるにあたり、他院への受診状況や患者の疾患の種類などを分析して継続的な受診の妥当性を検討すべき」(中野惠委員・健康保険組合連合会参与)といった意見が出た。
■「連携強化診療情報提供料」は診療所の算定回数の少なさを問題視する意見も
会合では「連携強化診療情報提供料」の評価のあり方なども議論した。当該報酬は紹介先医療機関が紹介元医療機関に診療情報を提供した場合の評価。ただし、日常的な医学管理を行う診療所等と専門的な医学管理を行う重点医療機関等との連携促進を目的とした評価のため、紹介先または紹介元の診療所等がかかりつけ医機能に関する施設基準(「地域包括診療料・加算」の届出など)を満たしていなければ算定できない。
算定回数は24年に大きく伸びたが、大部分が病院であることから井川誠一郎委員(日本慢性期医療協会副会長)は、「診療所の伸びが少ない理由が複雑な算定要件にあるなら、もっとシンプルにして算定しやすくしないと病院と診療所をつなぐ非常に重要な部分が欠落することになる」と問題視した。