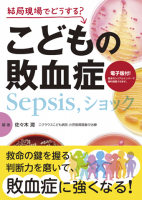お知らせ
【識者の眼】「合計特殊出生率が低下しても小児科医の必要性は下がらない」石﨑優子
小児科が「2020年度の専攻医の募集におけるシーリング」の対象になったことから、国が小児科医の必要性をどう感じているのかを考えさせられる。小児科が対象になった最大の根拠は少子化の進行により、将来、子どもの数が減っていくため小児科医の必要性が低下するという点にあるという。確かにわが国の合計特殊出生率は2005年に最低の1.26を記録した後、緩やかに回復しているもののここ数年は1.4近傍で推移しており、日本で生まれる子どもの数が減少していくことは間違いない。しかし、このことは小児科医の診る患者数が減ることも小児科医の業務が減ることも意味してはいない。
その理由として、最初に小児医療におけるインバウンドを考えてみる。法務省は2019年6月末の在留外国人数を282万9416人、過去最高との数字を出している。うち労働年齢の外国人は家族で来日することも多い。特に都市部の小児科では外国人患者の増加が著しい地域もある。日本で生まれた子どもでなくとも、子どもはみな小児科に来るのである。
次に学童期の6〜8%と言われる子どもの発達障害について考えてみたい。発達障害児の支援には、教育、福祉、医療の連携が必要とされる。発達障害に対応するのは児童精神科医と思われがちであるが、小児科医も深くかかわっている。その数字を一つ挙げると、小児の発達障害と心の問題に携わる一般社団法人子どもの心専門医機構による「子どもの心専門医」は専門医数554人のうち、日本小児科学会の専門医を有する者が241人と半数近くに上っている(2019年10月1日)。
年々増加している児童虐待に関しても、医療機関の虐待対応組織に主にかかわる診療科は小児科が78.6%と圧倒的に多いことが、2018年に行われた全国調査で明らかになっている。
最後に成人を迎えた小児期発症慢性疾患患者の医療の担い手を挙げたい。昨今トランジションとして注目されている問題であるが、成人後も小児科医のフォローを受ける患者も多い。
以上を考えあわせると「合計特殊出生率が低下しても小児科医の必要性は決して下がらない」のである。
石﨑優子(関西医科大学小児科学講座准教授)[小児科医][専攻医シーリング]