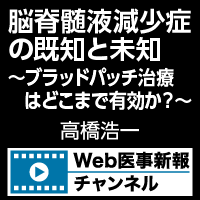お知らせ
【識者の眼】「傾聴するとは」西 智弘
No.5098 (2022年01月08日発行) P.62
西 智弘 (川崎市立井田病院腫瘍内科/緩和ケア内科)
登録日: 2021-12-22
最終更新日: 2021-12-22
- コーナー: OPINION
- 医療界を読み解く[識者の眼]
「傾聴」という言葉が人口に膾炙して久しい。
20年ほど前、教科書で紹介され始めたその言葉は、今では医師も、看護師も、そして学生の間でも知らないものなどおらず、病棟実習に来る学生たちの目標で「患者さんのお話を傾聴します」が立案されない日はない。
しかし、傾聴が広まってくるにつれ、「傾聴は何のために行っているの?」という当然の問いが現場の各所で見られるようになってきた。たとえば「患者さんの思いを一生懸命に『傾聴』しているにもかかわらず、患者さんが心を開いてくれないんです」とか、「傾聴を根気強く行っても、患者の悲しみを癒すことができません。何も変わらないんです」とかの疑問だ。
第一に言えることは、傾聴は患者を「変える」ために行うものではない。傾聴をすると患者の気持ちが変わることは確かにある。しかし、それはあくまでも傾聴を行った結果としてそこに行きつけた、というだけ。傾聴はあくまでも「患者自身が自ら、自分の意志に沿って自由に話せるように言葉の環境を設定すること」であり、医療者が患者から話を聞きだそうとするものではない。
そして第二に言えることは、「傾聴=患者の話に耳を傾けること」と誤解されている点である。指導者が「患者さんの話を傾聴しなさい」と告げる時、それが「そもそも話を聞けていない人たち」に向けた言葉であることはしばしばある。たとえば患者が「もう薬を飲みたくない」と抵抗した時に「先生が処方した薬だから決められた通りに飲んでください」と管理するのは「話を聞けない」典型例だ。ではその時に「じゃあ、薬を飲まない理由を教えてください」とベッドサイドに座って、20分ほど本人の訴え、ここでは「内服が多い」とか「過去に薬でアレルギーが出たことがあるから怖い」などの情報を聞き出したとして、それで「傾聴した」と言ってしまっていないだろうか。それは結局のところ、傾聴ではなく「優しい尋問」である。
傾聴とは、患者の感じ方として捉えるなら「この看護師さんを前にすると、ついついいろいろと話したくなっちゃうんだよな」と思ってもらえる技術である。その語りの中に、患者にとって大切な価値観が含まれていたり、自身の気持ちの整理につながっていくカギが隠れていたりする。いま、広く「傾聴」という技術が広まってきたがゆえに、その技術の本質的な部分が失われつつあることを危惧している。
西 智弘(川崎市立井田病院腫瘍内科/緩和ケア内科)[傾聴]