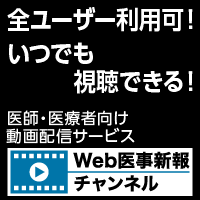お知らせ
【識者の眼】「ステロイドとは?」宮坂信之
No.5141 (2022年11月05日発行) P.64
宮坂信之 (東京医科歯科大学名誉教授)
登録日: 2022-09-30
最終更新日: 2022-09-29
- コーナー: OPINION
- 医療界を読み解く[識者の眼]
ステロイドは最も日本の医師が好んで処方する薬のひとつである。ステロイドは副腎皮質ステロイドホルモンを合成したものであり、抗炎症作用と免疫抑制作用を併せ持つ唯一の薬剤である。正確にはグルココルチコイドと言われる。
もともとはドーピングの目的でつくられた薬剤と言ってもよい。第二次大戦中に、どんなに疲れていようとも敵と遭遇しても勝つことができる兵隊をつくる「スーパードラッグ」が探されていた。これが副腎皮質ホルモンであることを見つけたのがケンドルとライヒシュタインである。これを臨床応用したのがメイヨークリニックのヘンチであった。ヘンチが関節リウマチ(RA)患者に投与して著効を得たことから、上記3人は1950年ノーベル医学生理学賞を得た。薬として合成したのはメルク社であった。しかし、RAの関節炎が良くなったのは一時的であり、その後はむしろ副作用に悩まされることになった。
ステロイドにもいろいろある。コルチゾールは速効型、プレドニゾロンは中間型、ベタメタゾンは遅効型である。セレスタミンという合剤(ベタメタゾン0.25mgとd-クロルフェニラミンマレイン酸塩2mg)は、開業医でよく使われる。鼻水・鼻づまりをはじめとする風邪症状の改善には使いやすい。セレスタミンにステロイドを入っていないと信じている開業医もいるほど(?)である。
しかし、ステロイドの長期連用は問題である。高齢者では耐糖能が落ちてくるし、骨も脆くなりやすい。眼圧が高く、緑内障の傾向がある人も少なくない。動脈硬化も進行する。
副作用を恐れて急速に減量すると炎症の再燃が起こる。長期連用を続けることによってネガティブ・フィードバック機構のために副腎の線維化が起こると、中止による離脱症候群が起こりやすい。うまく使えばメリットもあるが、下手に使うと毒ともなる。毒となっては薬の意味がない。
薬には有効性と安全性の両面があるが、両者をバランス良く使うことが必要である。
宮坂信之(東京医科歯科大学名誉教授)[副作用]