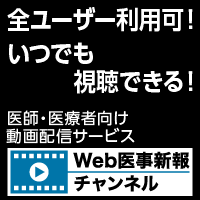お知らせ
【識者の眼】「歯科技工士を医科からも必要とされる“口腔機能回復士”に」槻木恵一
No.5142 (2022年11月12日発行) P.61
槻木恵一 (神奈川歯科大学副学長)
登録日: 2022-11-02
最終更新日: 2022-11-02
- コーナー: OPINION
- 医療界を読み解く[識者の眼]
歯科系の医療職は、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士の3種類があるが、歯科技工士養成校のほとんどが定員割れであり、歯科技工士の数は減り続けている。歯科の技術の進歩は著しく、CAD/CAMや3Dプリンターの歯科への応用が進み、必要とされる職種でありながら、現状は未来明るき職種とはなっていない。
歯科技工士の養成は2年制であり、カリキュラムは、歯科技工に特化した技術や材料の教育と基礎医学は歯の解剖が中心であり、いわゆる医療系のカリキュラムの王道である解剖学から基礎が始まり臨床系に向かう体裁とはなっていない。驚いたことに、技工が必要となる原因の歯科疾患について、病理学の講義はなく歯科疾患という病気の基礎を学んでいない。その理由は、歯科技工士法をみるとよく理解できる。
歯科技工とは歯科技工士法では、「特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することをいう」とされている。そして、それを業とするのが歯科技工士であり技術職であるので、患者を相手とすることは想定されていないのだ。歯科技工士と似た職種に義肢装具士があるが、決定的な違いは、義肢装具士は、「義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の製作及び身体への適合を行うこと」であり、臨床を業となすのである。
歯科の役割は、削って詰める時代から、オーラルフレイルの概念の登場で、口腔機能の維持と回復に移行している。すなわち、歯の修復物を作製し、それに伴う機能の回復までが治療の目標にならねばならない。これまで、歯科では入れ歯ができ、患者が適合に違和感がなければ治療は終了となっていることが多い。しかし、入れ歯を装着して、いかに食べられるようになったかが重要なのである。入れ歯を入れる前は、歯がないので軟らかいものを食べることが多く、うどんなど炭水化物主体の高カロリー低栄養食になっていることが指摘されている。一方、入れ歯は装着されても、それまでの食習慣は変わらず、野菜や肉などは、食べるように指導しないと変化しないことが多い。このように、歯科技工士は、単に技工物をつくるだけでなく、義肢装具士のように、臨床に携わる職種、すなわち口腔機能の維持回復に関与する職種に変化することが求められている。歯科技工士を口腔機能回復士としてリニューアルするのはどうだろうか。
この口腔機能回復士が、医科からも必要とされる職種として制度設計すれば、職種としても魅力が大きく高まることは疑いないし、医科歯科連携の要の職種となれば社会的意義も高い。是非とも多くの方に歯科技工士の発展に理解を頂きたい。
槻木恵一(神奈川歯科大学副学長)[オーラルフレイル]