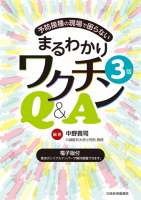お知らせ
【識者の眼】「デジタル母子手帳はだれのもの?」中村安秀
2023年6月9日、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定され、母子健康手帳(以下、母子手帳)とマイナンバーカード(以下、マイナカード)の一体化をめざす方針が示された。厚生労働省では同年3月に「母子保健情報のデジタル化について」報告書で、「こどもの健康履歴を本人又は保護者が一元的に閲覧し、こどもの健康を管理する」と記している。
母子手帳をデジタル化する際には、デジタル母子手帳は誰のものかという議論を避けることはできない。戦後まもない1948年に、日本の厚生省(当時)が母と子の記録を1冊の手帳の形にまとめた世界最初の母子手帳を「発明」した。母と子の保健医療情報を家庭で所有できる形にしたのが斬新だったが、66年に施行された母子保健法においても母子手帳の所有者は定められていなかった。実際には、母子手帳は妊娠中には妊婦の手元にあり、育児期には保護者が管理し、子どもの成長に伴い卒業や結婚などを機に、子ども自身に手渡されることが多い。母子一体という心象風景の中で、情報の所有者をあいまいにしたまま母と子のきずなを醸成してきた、日本的な保健医療システムであった。

アジアやアフリカの国々に母子手帳を導入するときに、最初に「母子手帳はだれのもの?」という問いかけを受けた。日本では考えたこともなかった問いであった。たとえば、子どもの権利条約をアジアで最初に批准したベトナムでは、母子手帳は子どものものであることを明示した。子どもが成人してからも予防接種データなどを活用することを考慮すれば、母子手帳は最終的には子どものものだという共通理解にたどりつく。子どもの視点から見れば、母子手帳は胎児時代からの健康情報記録であり、自分自身の成育史でもあるのだ。
デジタル母子手帳は子どものものであるという前提で、創り直すことが必要である。母親の妊娠に関する医療情報は、ドイツの母子手帳(Mutterpass)のように複数回の妊娠情報を記録できる形に切りわけてもいいかもしれない。母子手帳を保護者が管理できるのは18歳までと制限する必要が生じるであろう。管理者である母親が虐待したり死亡したりしたときの対応策も必須である。一方、デジタル母子手帳においても父親の役割を積極的に包摂すべきであろう。また、海外で受けた健診や予防接種の結果をどのように包含するのかというのも、グローバル時代の大きな課題である。
デジタル母子手帳に関しては、上記のように、様々な状況を想定した慎重な議論が必要である。まして、家族全体で共有する妊娠育児記録である母子手帳を、個人身分証明書でもあるマイナカードと一体化するためには、解決しなければならない課題が山積している。75年の歴史があり、普及率ほぼ100%という利用者から圧倒的な支持を受けている母子手帳について、丁寧な議論を経ることなく、マイナカードとの一体化を前提とした取り組みをすすめることはあまりにも拙速すぎる。
中村安秀(公益社団法人日本WHO協会理事長)[デジタル][母子手帳][マイナンバーカード][母子保健情報]