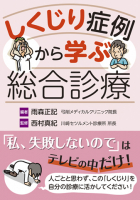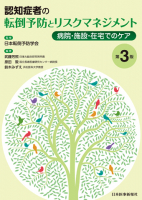お知らせ
【識者の眼】「医師法第20条と令和6年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」小田原良治
医師法第20条は、「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方箋を交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。ただし、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない」とされている。
この医師法第20条ただし書きについては、同じ趣旨の2つの通知が出されている。昭和24年4月14日医発第385号通知と平成24年8月31日医政医発0831第1号通知である。平成24年通知は、「医師法第20条ただし書きは、診療中の患者が診察後24時間以内に当該診療に関連した傷病で死亡した場合には、改めて診察をすることなく死亡診断書を交付し得ることを認めるものである」と、死後診察をすることなく死亡診断書を交付できる場合を示している。また、「医師が死亡の際に立ち会っておらず、生前の診察後24時間を経過した場合であっても、死亡後改めて診察を行い、生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できる場合には、死亡診断書を交付することができる」とされており、医師が死亡に立ち会っていなくても、死後診察を行うことにより死亡診断書を交付できることを改めて周知した。

平成29年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルは、医師が死亡に立ち会えなかった場合の死亡診断書交付について例示し、医師法第20条本文に基づく場合と、同ただし書きに基づく場合の死亡診断書交付の考え方を図示して死亡診断書交付の弾力化を図った。
今回公表された令和6年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルでは、生前に診察を担当していなかった医師が死亡診断書を交付できる場合の要件として、①同一医療機関内で情報を共有している場合や、生前に診療していた別の医療機関や患者の担当医師から生前の心身の状況を正確に把握できた場合で、生前の心身の状況に関する情報を正確に把握できていること、②死後診察を行うこと、③生前に診療を受けていた傷病に関連して死亡したと判断できること─の3つをすべて満たすこととしている。
Q&Aで例示もされているが、規範的内容となっており、平成29年度版より死亡診断書交付の対象範囲が限定されたように思われる。また、死亡診断書氏名欄について「記名押印は原則不可」と明記された。後日、死亡診断書を求められた場合に当該医師が在籍していなかった場合の取扱いなど確認の必要がありそうである。
小田原良治(日本医療法人協会常務理事・医療安全部会長、医療法人尚愛会理事長)[非担当医の交付要件]