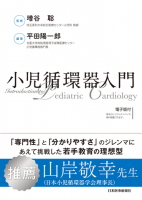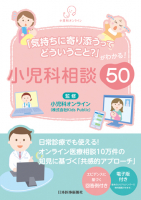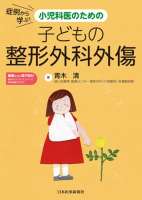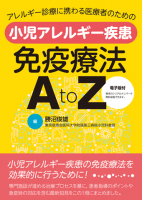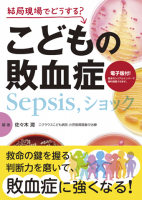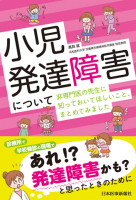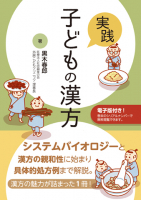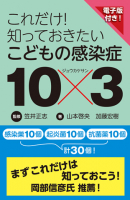お知らせ
【識者の眼】「子どもの声をどう聴くのか」小橋孝介
未来の礎となるすべての子どもや若者が健やかに成育できる「こどもまんなか」社会をめざして、こども基本法が2023年4月に施行され、12月にこども大綱が閣議決定された。今後各都道府県、市町村でこども計画が策定される。この中で求められるのが、子どもや若者の意見を聴き、これらの政策に反映させていくことである。こども家庭庁は24年3月に「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン〜こども・若者の声を聴く取り組みのはじめ方〜」を公開した。このガイドラインは各省庁や地方自治体職員を対象として、子どもの意見を聴くことの意義や方法、配慮すべきポイントなどをまとめたものだが、私たち医療者も子ども・若者に接し、アドボケイトとしての役割を果たすべき者として一読すべきガイドラインである。
日常診療の中で、特に子どもを対象とする場合、私たちはどの程度子どもの意見を聴いているだろうか?
本ガイドラインでは、たとえば乳幼児の意見を聴くことについて「第3章 声を聴かれにくいこども・若者の意見反映について」の中で「一人の人間として尊重し、意見を言えないと決めつけないこと」とされ、言葉による表現だけでなく、非言語的なコミュニケーションを観察し、意志を読み取ることで言葉にならない子どもの意見を聴くことを求めている。日本小児科学会が作成した「医療における子ども憲章」の中にも、子どもの権利条約に基づく「必要なことを教えてもらい、自分の気持ち、希望、意見を伝える権利」が掲げられている。私たちはすべての子どもの声を聴く姿勢を持たなければならない。
また、子どもが意見を持ち、声を上げていくためには、その成育の過程で「あなたはどう思う?」と意見を聴かれ、その意見が尊重される経験の積み重ねが必要である。そのためには、子どもの意見を聴いた結果、その意見がどのようにその後の意思決定に反映されたのか、また反映されなかった場合も、その理由を子ども自身にフィードバックする必要がある。しっかりと意見を聴き、フィードバックしていくことは、子ども自身が意見を持ち、その意見を自分の声として発信する力を育てることになる。医療現場において、子ども、特に乳幼児に対する関わりは父権的で一方的になりやすい。医療者側は子どもの発する声を聴くだけでなく、対話する姿勢を意識することも大切である。
小橋孝介(鴨川市立国保病院病院長)[アドボカシー][子ども虐待][子ども家庭福祉]