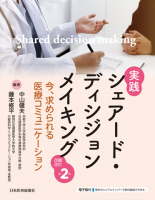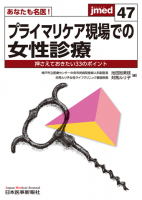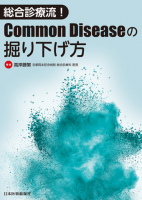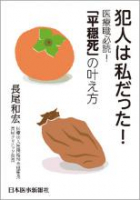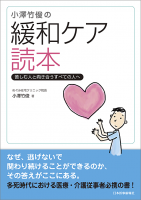お知らせ
【識者の眼】「ファクト認識の重要性」岩田健太郎
日本の医者は診断が苦手だと前々から思っている。いや、正確に言えば「苦手」というよりも「興味が乏しい」というべきか。
ある患者にある症状が生じたときに、「いったい、どうしてその症状が起きているのか」と一所懸命考えない。患者に起きている現象理解に関心が低いのだ。

代わりに行われるのは「ハウツー」である。あれを検査してこれを投薬して。ここには非常に関心が高い。ただし、妥当性が高いとは言えない。
昔の日本の医者は血液培養を取る習慣がなく、これを習慣化させるのにぼくらは随分苦労した。近年は血液培養を取らないけしからんプラクティスは激減したが、逆に「パターン認識」的ワークアップが増えたように思う。
熱が出ると、血液培養を取って、尿培養取って、胸部腹部のCTを撮って……臨床的には明らかに肺炎なのになぜ腹部のCTなのか。なぜ尿培養なのか。病歴や身体診察から患者の状態を推測せず、通り一遍のパターン認識的なワークアップをするのである。まさに「ハウツー」だ。
このような診断無視で検査、あるいは治療のパターン認識をしていると診断能力はどんどん痩せていく。患者に起きている現象に興味を失い、とにかく「ハウツー」でやるべきことをやり、あとは患者がよくなるかどうかは運任せである。
検査をするにせよ、治療を開始するにせよ、その前にやるべきは「患者に起きている現象を正しく把握する」という営為、アセスメントだ。ファクト認識と換言してもよい。
アセスメントとファクト認識に無頓着だと、診療そのものをしくじることになる。よくある誤謬が「大人の事情でアセスメントをひん曲げてしまう」行為だ。
たとえば、「主治医が術後の穿孔ではないと主張している」から、創部感染ではない(ことにしよう)というプレゼンを後期研修医にされることがある。主治医が「穿孔ではない(といいなあ)」と願う気持ちは痛いほどわかる。が、その思いは穿孔があるかないかのファクト認識とは独立したものだ。「お気持ち」に寄せてアセスメントに「お気持ち」を混ぜてはだめだ。「まぜるな危険」、である。
患者や主治医の思いは大事だが、それはアセスメントとは無関係だ。アセスメントをたてた「あとに」検討すべき事項である。「大人の事情」でファクトをひん曲げるのではなく、ファクトを冷徹に把握してからどう「願望」に寄せていくかがオトナの熟慮の見せ所である。
岩田健太郎(神戸大学医学研究科感染治療学分野教授)[パターン認識][アセスメント]