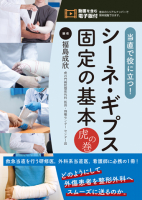お知らせ
【識者の眼】「脳が生み出す言葉:再帰性発話と脳の不思議」大沢愛子
先日、日本高次脳機能学会の学術総会に出席した。以前、日本失語症学会と名乗っていた本学会は、失語症をはじめとする高次脳機能とその障害の研究の発展を図り、関連学会と連携しながら、広く知識の交流を求めることを目的として活動しており、脳機能にとどまらず、人の動作や行動、心理、活動、さらには社会面まで幅広く対象としている。
リハビリテーション診療においても、脳卒中や脳腫瘍、外傷性脳損傷、認知症などに起因する脳機能の低下により行動や活動に問題をきたす人の治療を行っており、失語症や失行症、記憶障害などの患者に日常的に接する機会も多い。しかし、その症状の多彩さに触れるたびに、脳というのは本当に不思議な臓器だと感じる。
たとえば言語に注目すると、ひと言で失語症といっても、患者一人ひとりの話し方や理解の様子は異なる。ブローカ失語やウェルニッケ失語などの分類が示すように、損傷部位によって話し方や理解の特徴に類似点がみられるものの、実際のコミュニケーションの様子は患者ごとにまったく異なる。
具体例を挙げると、ほとんど言葉を発することができない重度の失語症者で、会話の文脈に関係なく、場面を問わずに不随意的・常同的に繰り返される発話を“再帰性発話”と呼ぶが、発する言葉や音は患者ごとに異なる。同じ左中大脳動脈領域の広範な梗塞巣を有するにもかかわらず、ある人は「ひゅー。ひゅー」としか言わず、別の人は「ほだね。ほだね」と繰り返す。重度の失語で短い言葉しか話せないかと思えば、「あの人があの人やからあの人やねん」「あの人やったというのはあの人やからな」など、助詞や助動詞が必ず挿入され、「あの人」という言葉を用いた多様な表現を繰り返す症例も報告されている1)。同じ“再帰性発話”という症状をとっても、1つとして同じ発話がないことに驚かされる。
そもそも近代の失語症研究は、1861年のPierre Paul Brocaによる何を聞いても「タン・タン」としか答えない患者の症例報告から始まっており、“再帰性発話”という症状と症例は、世界中で高次脳機能を勉強する者で知らない人はいないと言われるほど有名である。
しかし、150年以上が経過し、脳機能画像評価やAIを用いた解析技術が発達した現代においても、なぜ特定の言葉や音しか発声できないのか、またどうしてその特定の言葉だけを発するのかについては十分に解明されていない。明確な発症メカニズムや治療プロトコルが確立している分野と比べると、脳に関する領域はまだまだ未知の部分が多く残されている。
損傷された言語機能を駆使して、なんとか感情を表出しようとする患者の症状発現メカニズムを探ることは、コミュニケーション障害を少しでも軽減し、人間らしい生活を取り戻すためのリハビリテーション治療の第一歩である。多くの人に失語症をはじめとする高次脳機能に興味を持って頂ければと願う。
【文献】
1)松田 実:高次脳機能研究. 2020;40(2):131-42.
大沢愛子(国立長寿医療研究センターリハビリテーション科医長)[失語症][再帰性発話]