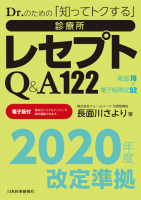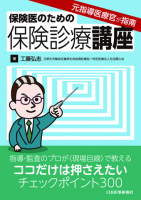お知らせ
■NEWS 新たな地域医療構想に沿った急性期入院料のあり方などを議論―入院・外来分科会
診療報酬調査専門組織の入院・外来医療等の調査評価分科会は5月22日、2026年度診療報酬改定に向けた個別事項の議論を開始した。この日のテーマは急性期入院医療。急性期病院を拠点的な機能を担う施設と高齢者救急などの機能を担う施設に再編成していく、新たな地域医療構想に沿った入院料のあり方を巡り、意見が交わされた。
2040年頃を見据えた新たな地域医療構想では、医療機関機能報告を創設。都道府県はその結果を基礎データとして地域における医療機関の機能分化と再編を目指す。このうち急性期入院医療は、急性期拠点機能/手術や救急医療等の医療資源を多く要する症例を集約した医療の提供と、高齢者救急・地域急性期機能/高齢者をはじめとする救急患者の受け入れや入院早期からのリハビリテーションの提供等をそれぞれ担う病院間の役割分担を推進する。

前者の急性期拠点機能には「総合入院体制加算」や「急性期充実体制加算」を算定する病院が主な対象になるとみられている。
厚労省の提出資料によると、「急性期一般入院料1」算定病院のおよそ半分は、地域包括ケア病棟などを併せ持つケアミックス病院。ケアミックス病院とそれ以外の一般病院を比較すると、病床規模の大きい施設の割合、救急搬送の地域シェア率、「総合入院体制加算」及び「急性期充実体制加算」の算定率が高いのはすべて一般病院であり、両者が地域で担う機能に違いがあることがうかがえた。
■小規模医療圏では拠点的役割担っても「急性期充実体制加算」を算定できず
また二次医療圏の分析データをみると、救急搬送件数は人口規模の大きな二次医療圏ほど多く、「急性期充実体制加算」や「総合入院体制加算」の多くが人口20万人超の二次医療圏で算定されていた。地域のシェア率でみると人口規模の小さな医療圏にも地域の救急搬送の大部分をカバーしているシェア率の高い病院はあるものの、これらの施設の大半が「急性期充実体制加算」や「総合入院体制加算」を算定していなかった。
このため厚労省は、①医療機関機能をより重視する新たな地域医療構想を踏まえた急性期の入院基本料のあり方、②小規模医療圏で救急搬送受け入れの拠点的役割を担う病院があることも考慮した、急性期の拠点的な機能に対する評価のあり方―を検討課題として提示した。