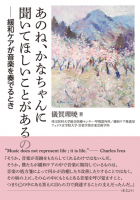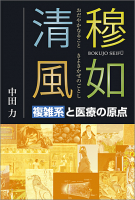お知らせ
大学院に行かなかった医者の「基礎医学大学院・留学の勧め」[炉辺閑話]
私は医師として好きなことをしてきており、後悔はあまりありません。その中で「若い頃に基礎の大学院に行けばよかった。そうすればもっと成長できた」と時々思います。
1981年に医学部を卒業して、故郷の鹿児島大学病院で研修を始めました。当時は何となく循環器に興味がありました。学生の頃に習った生理学的な講義が面白かったからです。しかし、循環器内科医になろうと強く思っていたわけではなく、糖尿病の患者さんを受け持つと「糖尿病診療は面白い!糖尿病内科医になろうかな?」と思った時期もありました。その時に重症心不全症例を受け持ち、当時のラシックス・ジギタリスによる治療が上手くいきました。この患者さんが骨格筋障害も合併しており、それを研修医の私が神経内科に相談したところ果たしてそうだったという経験から循環器内科医になりました。その後は、カテーテル専門医になろうと思ったり、基礎実験で動脈硬化を勉強したいと思ったりしましたが、当時の教授の勧めで心エコーを専門とすることになりました。26歳です。

心エコーを始めて10年ぐらいは「エコーって少し面白いな」ぐらいでした。38歳のときにマサチューセッツ総合病院の心エコーラボに留学する機会を得て、生涯の師匠となるボブ(Dr. Robert A. Levine)に師事することができました。飛び級で16歳で高校を卒業し、高校生のときに全米top 10 talented high school studentsに選ばれた超秀才です。心エコーを使った僧帽弁の研究を一緒にしましたが、僧帽弁尖の動きをニュートン力学から考えることに感銘を受けました。ニュートン力学の知識自体(と言ってもせいぜい「力=質量×加速度」、程度)は私も持っていましたが、目の前の心エコー図画像の弁尖の動きを力学から考えるということはまったくできませんでした。世界のトップレベルをみたくて留学しましたが、「なるほど、これが世界の頭脳か!」と感銘を受けました。
その後、私も少しは成長し、心エコーがとても面白くなり、現在でも心エコー図からみえてくる病態生理の疑問点を若手医師と一緒に研究・解明したりして、それなりに楽しく過ごしています。しかし、私が考えることができる疑問(これが創造の出発点だと思います)が狭い範囲に限定されていると最近つくづく思います。たとえば、収縮後期僧帽弁逸脱は、弁尖・弁輪が大きくなる病気であり、健常者の2~3倍になる場合もあります。すなわち、「弁尖過剰拡大症」がこの病気の本態で、逸脱自体は二次性です(詳細は省略)。この弁膜症の弁尖細胞にどのような異常があるのか?見当がつきません。この病気ではしばしば外科手術をしますので、そのときに弁尖組織を入手することは可能です。若い症例では、「手術後には弁尖の拡大は止まるのか?」という重要な疑問が残りますが、私自身どのようにアプローチすればよいのか?まったくわかりません。「自分に基礎医学の素養があれば弁膜症をもっとよく理解できるのに」と思います。
初期研修や専門医研修をしている若いお医者さんへぜひ大学院・留学で基礎医学を勉強することをお勧めします。解剖・生理・生化学・分子生物学・遺伝学といった生物学に近い視点から病気や患者さんをみるとより深く理解できて、(運が良ければ)より良い診療を行うことができると思います。20歳代がベストですが、30歳代でも遅くありません。