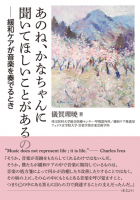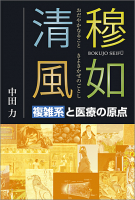お知らせ
反射材を備えた医療・救護活動[先生、ご存知ですか(86)]
能登半島地震の現場で
2024年の元日に発生した能登半島地震では、最大マグニチュード7.6が記録され、建物の倒壊だけでなく火災も発生しました。夜間は辺り一面真っ暗な状態でした。DMATをはじめ、多くの関係者が支援に入りましたが、道路事情が悪く、到着するまでに多くの困難があったそうです。
さて、現場で活動した関係者からの報告によると、暗い中では車両の前照灯のみが頼りであった、どの関係者の車両なのか近くまで行かないとわからなかった、とのことです。今回のように、夜間に暗い所で活動する際には、車両や自身の視認性を高めること、どの関係者の車両か一見してわかるようにすることが必要です。

ある救急隊員の死
2012年の1月に、夜間の高速道路上で救急自動車が接触事故に遭いました。事故の影響で、車両は全灯火能力を喪失した状態になり、路上に停車していました。すると、視認性の悪さから、後続の車両が救急自動車に衝突し、救急隊員が殉職するという痛ましい事故が発生しました。
夜間に高速道路上に停車している無灯火の車両を遠方から発見することは困難であり、停止車両を発見しても避けることができませんでした。本件を受けて、夜間や暗闇での活動時において、車両の視認性を保つべく対策を講じることが求められました。
関連学会では、視認性に優れた救急自動車のための検討会などを経て、救急自動車に再帰性に富んだ反射材の使用を推奨すべく、提言を関連省庁に行いました。再帰性に富んだ反射材の設置は、夜間や薄暮時などでも高い視認性を有すること、動力を必要とせず比較的安価であること、費用対効果に優れており車両付近で活動する関係者の安全確保や二次災害の防止にきわめて有効な処置であること、が結論づけられました。そして、全国の消防本部において、救急自動車等の更新または整備に併せて、再帰性に富んだ反射材を取りつけることが推進されました。
安全のために反射材を積極活用へ
法律では、他の交通の妨げにならないこと(派手すぎて迷惑にならないこと)、車両の前面に赤色の反射材を用いないこと、車両の後面に白色の反射材を用いないことが定められています。これらをふまえた上で、どのような色(黄色や緑など)をどのようなデザインで貼るかは個々の判断によります。
車両の輪郭がわかるよう、あるいは文字がわかるように(POLICEなど)反射材が貼られているのを目にします。英国では緊急車両に取りつける反射材の模様をバッテンバーグ・マーキングとして統一し、かつ、その配色によって消防、救急、警察等、どの機関の車両かが容易に識別できるようになっています。いずれにせよ、災害や緊急現場に臨場して活動を行う可能性がある場合には、必ず車両に反射材を貼るようにして下さい。
また、車両だけでなく、個々の衣服にも反射材を貼る必要があります。消火活動を行う消防隊員に対しては、防火服の腕、足および胴体の各部分に一定以上の大きさの再帰反射材を取りつけることになっています。災害や事故時に活動する関係者を守るために、着用する衣類に対しても反射材を貼って下さい。