お知らせ
『職業としての学問』/私的「職業としての学問」/最後のシンポジウム[なかのとおるの御隠居通信 其の9]
人生を65歳で振り返るというのは少し早すぎるかもしれません。でも、長年従事してきた「職業としての科学」から退いた今、考えてみても罰は当たらないでしょう。ということで、かなり真面目に書いてみました。
『職業としての学問』
『職業としての学問』といえば、ドイツの社会学者、かのマックス・ウェーバーの名著である。とても有名だし内容の濃い本だが、文庫で80ページほどとえらく短い。

もとは大学生向けに行われた講演の記録である。1917年11月というから、第一次世界大戦の末期、戦況が悪化するドイツで行われたものだ。そのこともあるのだろうか、論調は必ずしも明るくない。学問を職業にするためのハードルがえらく高く設定されているし、聴講した学生はさぞかし暗い気分になって、アカデミアに進むのをためらってしまったに違いない。
敵国である米国を悪しざまに言うとか、学問と宗教との比較とか、時代にそぐわないところもあるが、本質的には現在に通じるところも多い。たとえば、科学と芸術の比較において、「科学の世界では、科学者が成し得たことは、10年、20年、50年で古びてしまいます。これは科学に課せられた宿命です」(岩波文庫『職業としての学問』から、以下同じ)といったようなところ。
数年前に、文化勲章受章の大先生といっしょに文楽を鑑賞したことがある。演目は確か近松門左衛門の名作「女殺油地獄」だった。その時、いみじくも「仲野君、近松というのはすごいなぁ。300年たっても作品が鑑賞に堪えるんや。我々の業績はいくらいいやつでも30年が限度やろ」とおっしゃったのをよく覚えている。
「科学があるひとの『職業』として価値あるものか」という問いかけには感動すら覚える。そんなもん自明やろ、イエスとちゃうんかと思われるかもしれないが、必ずしもそうではない。というのは、ずっとその疑問を抱きながら40年近くも長い研究者生活を送ってきたからだ。
私的「職業としての学問」
定年で完全に研究から離れた。もったいないと言ってくださる方がおられたのはありがたかったけれど、ずっと前から決めていたことだ。理由はいくつかある。ひとつは、相当な幸運に恵まれてやってこられたけれど、もうそろそろ運が尽きるに違いないという不安感である。
ウェーバーでさえ、「わたしが早いうちに正教授に任命されたのが個人的に単なる偶然に負うところが多い」とか「学者生活は狂った運まかせとなります」と書いているのだから、わたしレベルが感じるのは当然のことだ。そう考えると、運が尽きる前に辞めたいなどというみっともない言い訳をせずに済ませてくれる定年というのは、じつにありがたいシステムではないか。
ずっと研究を続けたいとおっしゃる先生には頭が下がる。そういう先生には科学に「職業としての価値」があったのだ。しかし、わたしの場合は、定年で辞めてすぐ、驚くほど急速に研究への興味を失った。
科学はわたしにとって「単なる職業」にすぎなかったのかもしれない。そう思うとトホホな感じがしないでもないけれど、まぁしゃぁないですわな。じゃぁ研究者生活はつまらなかったのかといわれると、決してそのようなことはない。成果を論文として発表するのは当然ながら、それ以上に、いろいろな人との出会いが愉しかった。
最後のシンポジウム
昨年11月、人生最後と決めていたシンポジウムに出席した。研究やめたんちゃうんかいっ! と言われそうだが、現役時代からの持ち越しで、研究領域の評価者みたいな仕事だったのでいたしかたなし。
タイトルは「Totipotency and Germ Cell Development(全能性と生殖細胞の発生)」で、研究者生活後半のテーマだったエピジェネティクスに関連した研究についてのシンポジウムだった。聞いていて、何よりも時代の流れを強く感じた。
というのは、昔ながらの生物学実験から、ビッグデータによるデータサイエンスへの大転換があって、この10年程の間にすっかり様変わりしたからだ。悲しいかな、理解はできるが、自分では解析する能力はない。あかんやろ。これも定年での引退を決意した大きな理由のひとつだった。
参加者たちとの会話が思っていた以上に盛り上がった。これで最後のシンポジウムと決めているので、ほとんどの人たちとは今生の別れである。昔話などをしながらしみじみとこれまでの交遊を嚙み締めた。
すごく嬉しいこともあった。同じテーマの研究内容をお互いに熟知している外国人研究者との初めての顔合わせである。ライバルであると同時に同士だ。ここで会ったが百年目ではなくて、「ようやく会えましたなぁ」と、互いに大興奮だった。こんな時、研究をしていて本当に幸せだったと思う。

こういった意味で、わたしにとっての研究は、単なる職業というよりも、人生を楽しむためのステップとしての職業だったのかもしれない。あぁよかった。
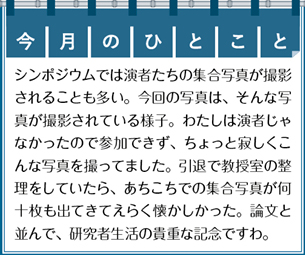
仲野 徹 Nakano Toru
大阪市旭区生まれ。1981年阪大卒。2022年4月より阪大名誉教授。趣味は読書、僻地旅行、義太夫語り。『仲野教授の笑う門には病なし!』(ミシマ社)大好評発売中!











































