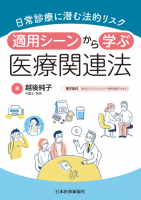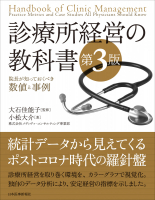お知らせ
【識者の眼】「医療現場におけるハラスメントと対応に向けて必要なこと」安藤明美
近年、ハラスメントという言葉をよく耳にするようになった。セクハラ、パワハラ、カスハラ……医療現場ではどうか。愛知県医師会が実施した調査では、病院職員の72.8%が何らかのハラスメントを経験しているとされる1)。決して他人事ではない。放置すれば医療従事者の士気も下がり、心身の健康にも悪影響をもたらす可能性がある。また、そのような状況では医療の質も低下し、医療事故のリスクが高まる。
ハラスメントについて正確な知識を持つ医療従事者がどれほどいるだろうか。各医療機関の最高責任者がハラスメント対策の重要性をどれほど認識し、職場環境改善のための施策をどれほど実行しているだろうか。多くの医療機関の最高責任者は、崇高な精神を持ち医療に情熱を注いできた大先輩方だ。ここまで医療界をけん引してきたことに敬意を表したい。しかしながら現代の患者は、先輩方が若手医師の頃に出会った患者とは時代背景も価値観も大きく異なる。国民の医師や医療機関に対する考え方が変化している中、職員を守りながら質の高い医療を提供し続けるためには、新たな価値観と使命感を持った病院運営が必要だ。

ハラスメントの中でも医療者の間で関心が高いペイシェントハラスメントは、「患者・家族等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、病院職員の職場環境が害されるもの」と定義されている。新潟県病院局によって公開されている「ペイシェントハラスメント対策指針」は、職員をハラスメントから守る施策立案の参考となる。
医療機関におけるハラスメント報告の多くは看護職だが、医師も例外ではなく、外科医の間でハラスメントが蔓延しているという報告もある2)。ところが、ハラスメント防止対策については、研究がほとんどされていない。この要因には医師自身、自分たちがハラスメントを受けているということを認めたくないという思いや、社会に出て初めて経験する職場が厳しかった場合、ハラスメントを受けているということにすら気づかないケースもあると考えられる。
また、昨今では医療機関で最も立場の弱い存在ともなりうる臨床研修医が、医療職以外から受けるハラスメントも話題にのぼることが増え、臨床研修医が安心して研修を継続するためのサポート体制の構築も重要と言える。その一方で、いわゆるハラスメントハラスメントに悩む指導医の声も上がっており、研修医を指導する医師のサポートも必要だ。
医療現場で安心して働ける環境を整えることは、患者に対する最良のケアを提供するための基本となる。まずは今ある問題視されていない身近なハラスメントの存在を認め、正しい理解と対策の実行によって職員が安心して働く環境を実現したい。
【文献】
1)天野 寛, 他:日医療病管理会誌. 2011;48(4):221-33.
2)Halim UA, et al:Br J Surg. 2018;105(11):1390-7.
安藤明美(安藤労働衛生コンサルタント事務所、東京大学医学系研究科医学教育国際研究センター医学教育国際協力学)[産業保健][ハラスメント]