お知らせ
【私の一冊】ヴァン・ゴッホ
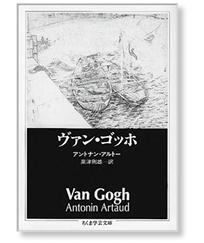
アントナン・アルトー著、粟津則雄訳、ちくま学芸文庫(原著1947年)。狂気の淵で生きた詩人にして前衛演劇の実践者による傑作美術論

精神障害者でなく「狂気」当事者
詩人にして現代演劇の祖であるアントナン・アルトー(1896〜1948)の晩年の評論である本書は、こう書き始められる。
「人びとは、ヴァン・ゴッホが精神的に健康だったと言うことができる。彼は、その生涯を通じて、片方の手を焼いただけだし、それ以外としては、或るとき、おのれの左の耳を切りとったにすぎないのだ。」
これらは、画家ゴッホの精神障害のエピソードとして知られている。だが、パリのオランジュリー美術館でのゴッホ展を論じるアルトーは、そうした行為は「いたんだ社会」のなかでは健康の証拠だと主張してみせる。淡々とした散文でありながら、私たちの常識を脱臼させるこうした表現が随所にみられ、ゴッホ論に留まらず詩人による絵画論としても評価が高い。
例えば、アルトーはゴッホ展を「歴史における一事件」と呼ぶ。ゴッホの絵を見たことがあれば誰でも、自然の向日葵を眺めるとき、キャンバスの中のねじくれた向日葵と無意識に比べてしまうだろう。つまり、現実の向日葵の運命も私たちの視覚も変えられたのだから、まさに歴史的事件なのだ。
彼自身が1936〜46年の間は精神病院に監禁され、この評論は1947年にイヴリー療養所で書かれたことを考えれば、アルトーはゴッホと共闘する「当事者」の立場で語っているとも言える。現代では精神障害者はもちろん、がんサバイバーや認知症の人々など本人自身が自分の苦しみを生きた経験として語ることが増え始めている。患者が同病者や一般人に向けて語る言葉は、なかには医師の立場からは首をひねる内容もあるにせよ、症状を訴えるときとは全く異なった息吹を放ち、医師としてはっとさせられる発見も数多くある。
本書はそうした当事者による表現の先駆の一つとしても読める。











































