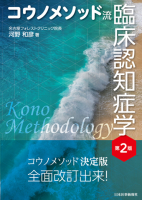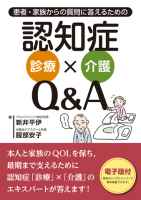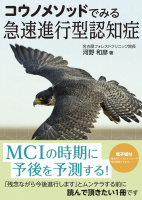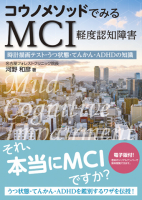お知らせ
せん妄[私の治療]
せん妄とは,身体疾患や薬剤などにより惹起され,認知症など他の神経認知障害では説明できない,急性の脳機能不全(急性に発症する注意・意識・認知の障害)である。また,幻覚・妄想,情動・気分の障害,興奮・焦燥,拒絶・攻撃性などの多彩な精神症状を呈する。せん妄は高齢者に発症しやすく,かつその転帰を不良にする。
▶診断のポイント
日内変動の有無,発症の仕方(急性か緩徐か),元来の認知機能について,看護師や家族から情報を聴取する。また,治療が異なるため,物質(アルコール,ベンゾジアゼピン系薬剤など)離脱によるせん妄かどうかを評価する。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
抗精神病薬は様々な副作用(錐体外路症状,代謝系の副作用,高プロラクチン血症,悪性症候群など)を惹起しうる。特に高齢者は抗精神病薬の副作用が惹起されやすく,死亡のリスクが上昇し,錐体外路症状は転倒や誤嚥の原因となる。したがって,抗精神病薬以外の安全性の高いせん妄治療薬が求められる。せん妄は過活動型,低活動型ともに睡眠覚醒リズムの障害が基底にあることから,その改善を目的に鎮静・催眠作用を有する向精神薬が使用されうる。
そこで筆者は,安全性の観点から,抗精神病薬以外の催眠・鎮静作用を有する向精神薬(ベンゾジアゼピン系薬剤以外)を優先している1)。2~3日で改善が得られない場合,使用中の薬剤を中止した上で,次の手に進む。せん妄に対して使用された薬剤が漫然と継続されることを避けるため,せん妄(もしくはリスク状態)が改善した2~3日後に,使用中の薬剤を不眠・不穏時の頓服とし,可能な限り中止する。また,せん妄発症のリスクとなるベンゾジアゼピン系薬剤は可能な限り漸減中止する。

残り1,983文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する