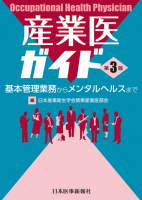お知らせ
【識者の眼】「組織レベルのヘルスリテラシーと現実」黒澤 一
過去3回にわたり本欄で医師の働き方改革を取り上げてきた。先日、産業医などの産業保健職が集まる学会に参加し、思うところがあり、引き続き本欄のテーマとすることにした。
学会企画のうち、医師の面接指導のあれこれについてのシンポジウムに筆者も登壇した。2024年4月に始まったばかりの制度だし、慣れないことばかり。改正医療法の中で、労働安全衛生法に規定された産業医のアイデンティティをどこに見つけるのか。産業医生涯研修単位付きという事情があるにせよ、実際の関心も高かったのだと思う。会場はほぼ満席になった。自分の発表の如何はともかく、各登壇者の充実した内容と会場の賑わいが嬉しかった。だが、同時に、モヤモヤとする部分もあった。

リテラシーはもともと読み書きの能力を意味する言葉だそうだ。転じて、特定の領域の知識や能力の意味にもよく使われる。例えば、ITリテラシーといえばインターネットなどの情報技術の知識や活用能力を指す。また例えば、喫煙や大量飲酒などの望ましくない生活習慣を持つ医師に対しては、ヘルスリテラシーの欠如が発露していると解釈したりもする。望ましくない生活習慣の害は医師であれば誰もが知る知識なので、健康影響の重大性と自分の行動との矛盾を見抜く洞察や行動変容への実行能力がないという意味だろう。
リテラシーを組織のレベルで考えるとどうなるか。例えば、健康増進法によれば、大学や行政機関は第一種施設であり、敷地内全面禁煙が原則だ。それなのに、敷地内全面禁煙が達成できていない大学は少なくない。法律にある例外規定を抜け道として、喫煙所を構内に置いているのだ。研究や教育の場であり社会の模範たるべき大学に、例外規定を適用する正々堂々とした理由は考えにくい。全面禁煙にふみ切れない大学に対するリテラシーを持つ職員個人がかかえる忸怩たる思い。なかなか埋められない溝。愚痴をこぼす他大学保健関係者の姿を筆者は何回も目撃している。
医師の働き方改革では、研鑽について労働時間を「切りわけ」する医療機関のローカルルールをつくることになっている。実効あるルールづくりをしている医療機関がある一方で、アリバイ的なルールづくりにとどまる医療機関がある。例えば、法律や通達の意を汲みつつ現場の医師の意見も聞いて、コンセンサスを重視するのはリテラシーのある医療機関だろう。反対に、法律を都合よく曲げて解釈し、労働時間にカウントすべき時間まで労働時間外とすることを使用者側が一方的に決めてしまう医療機関だったら、組織のリテラシーの低さに医師の不満は鬱積してしまう。ある雑誌の特集では、リテラシーのない病院のまずい対応の挙句、「結局何も変わらない」「何をやっても無駄」、制度に対する批判的な残念な声が並んでいた。医療機関にリテラシーのある医師個人がいても、組織とのミスマッチの壁が高ければ高いほど、匙を投げてしまう者が増えるだけ、ということだろう。
ただ、今回の問題は旗幟を明確にできる禁煙の問題とは異なる。正論ばかり言うつもりはないし、法律の抜け道を探索するやり方も非難したくない。改正医療法に基づく医師の働き方改革と病院の経営や地域医療維持には、両立しにくい部分があるからだ。リテラシー側の立場に共感する医師もいれば、経営や地域の医療事情を優先せざるをえない立場の医師もいる。ある意味どちらにも理がある。埋められない溝が見て見ぬふりをされている、これが筆者のモヤモヤの一端であり、正体に近いのかもしれない。
黒澤 一(東北大学環境・安全推進センター教授)[医師の働き方改革][研鑽のルール]