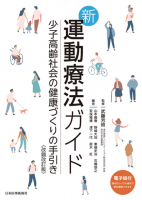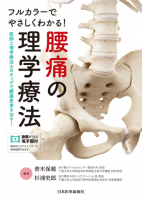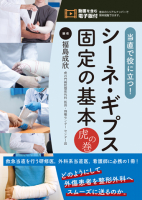お知らせ
【識者の眼】「鵜飼から考える人の摂食嚥下機能」大沢愛子
先日、初めて長良川の鵜飼見物に行ってきた。岐阜の夏の風物詩として受け継がれ、1300年以上の歴史があるとのこと。正倉院にある702年の美濃国とされる戸籍の中に「」という記述があり、鵜飼を生業としていた集団の出身者と推定され、長良川鵜飼が1300年以上の歴史を持つとする由来とされている1)。室町時代には足利義教なども観覧したそうで、観光のためのデモンストレーションと思い込んでいたが、見せる(魅せる)ものとして鵜飼をおもてなしの手法に取り込んだのは織田信長。それ以来、徳川家康、秀忠、松尾芭蕉、近いところではチャップリンなどたくさんの著名な歴史上の人物が鵜飼見物を楽しんでいるが、単なる見せものではなく、実は漁をしている姿を見せてもらっているのだと知って驚いた。
匠は漁の直前に、鵜の首に麻の縄をかける首結いという作業を行うが、小さな魚は鵜が食べられるよう、一方、大きな魚は鵜が食べられず吐け籠に吐き出せるよう、それまでの経験と勘によって縄を結う強さを決めているのだという。鵜には、もともと、食道の下端に袋状の部分があり、魚などの餌をためることができる。なるほど、首結いの強さでその部分の容量を調節し、さらに漁の際に縄を引くことで食道を狭め、魚の通過を制限しているのかと推測する。

人にはこのような芸当はとてもできない。人が食物や飲み物を飲み込む際に、ごくわずかな時間だけ食塊がたまる喉頭蓋谷と呼ばれる場所がある。固形物の咀嚼嚥下では、口腔内で食塊が粉砕され、唾液と混和された食物が嚥下反射惹起前に咀嚼運動に伴って咽頭に送り込まれる。すぐに嚥下反射は起こらず、そのまま咀嚼が続けられ、食塊は喉頭蓋谷領域に集積されるが、集積した食塊も通常は嚥下反射とともに速やかに食道に送られ、集積される容量もわずか数ミリリットルである。しかし脳卒中や神経変性疾患などにより摂食嚥下障害をきたすと、嚥下反射が起こっても食塊を十分に食道に送ることができず、喉頭蓋谷や梨状窩(梨状陥凹)に多くの食塊が残留する。この残留物は嚥下後に気道に受動的に入り込み、嚥下後誤嚥の主な要因となる。
この咽頭残留を防ぐため、摂食嚥下リハビリテーションではゼリー食やペースト食などに食形態を調整して丸呑みに近い嚥下を誘導したり、頸部や体幹の角度を調節したり、増粘剤の濃度を本人の機能に合わせて調整したりする。しかし、喉頭蓋谷や梨状窩の容量は人によって様々に異なり、容量の少ない人は誤嚥を防ぐことがむずかしい。さらに人では咽頭を越えればもはや随意的に食塊の流れを調整することは不可能であるが、鵜はいったん飲み込んで袋に溜めていた魚を吐き出すこともできるようだ。遊覧船で心地よい川風に吹かれつつ、人にもこのような機能があれば嚥下後誤嚥などで苦労しないのに、と羨ましく思う鵜飼の夜であった。
【文献】
1)岐阜市鵜飼観覧船事務所公式サイト:ぎふ長良川の鵜飼.
https://www.ukai-gifucity.jp
大沢愛子(国立長寿医療研究センターリハビリテーション科医長)[嚥下後誤嚥]