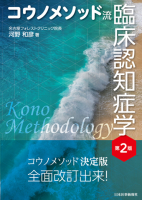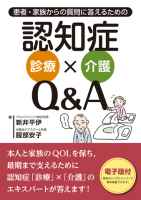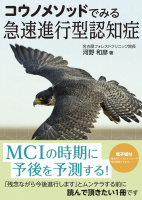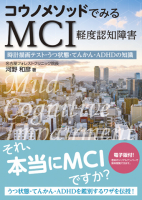お知らせ
【識者の眼】「スティグマとしての精神医療」太刀川弘和

6月20〜23日に札幌で開催された第120回日本精神神経学会学術総会(会長:河西千秋札幌医科大学教授)では、「真に役立つ精神医学」というテーマで100近くのシンポジウムが組まれ、参加登録者数は延べ8000人以上と過去最大の規模になった。
同大会に招待されたデンマーク・コペンハーゲン大学のノルデントート教授による特別講演は大変印象深いものだった。教授によれば、デンマークでは最近精神医療費の国家予算を20%増加させることができたという。この国家施策の画期的変化の理由として、精神疾患は生涯で4人に1人以上が罹患し、がんや脳梗塞よりも罹病期間が長く、本人、家族への負担や経済損失額がはるかに大きいという国際的エビデンスが得られたこと、多くの有名人が精神障害の罹患を告白し、コロナ禍で国民的なメンタルヘルス対策が政府に求められたこと、さらにこれをふまえて医療界、NPO、患者団体が一体となって精神疾患の国家施策に声を上げたことを列挙し、その成果を自賛した。
ひるがえってわが国の精神医療はどうかというと、入院費が身体科の数分の1しかなく、患者数に対する精神科医師数は他科の3分の1、看護師数も3分の2でよいとする精神科特例が長年続いた。この背景には、1964年に駐日大使が刺された事件以降、精神障害者へのスティグマ(属性に対する否定的で誤った態度)化が生じ、精神科の長期入院を認めた国の隔離主義的政策があった。そして長期入院者が多いことを世界から指弾されると、今度は入院患者数を減らす地域移行が奨励された。地域移行を率先して実施した精神科病院は、稼働率低下によって経営困難に陥った。また、地域移行した患者の受け皿である精神科クリニックは、診療に忙殺された。さらに今年6月の診療報酬改定では、通院・在宅精神療法にかかる時間を10分刻みで報告させ、30分未満の点数は下げ、60分以上の点数を上げる措置がとられた。1日に30人以上の再診患者を診るのが普通の精神科クリニックの算定をこのように変更すると、多くのクリニックは立ちいかなくなる恐れがある。
ここまでの説明でおわかりのように、日本の精神医療は、特にその政策誘導があまりに表面的、日和見主義的で、その背景には精神医療を医療とみていない国の偏見があるのではないだろうか。実際、精神疾患が5大疾病の1つになって久しいにもかかわらず、中央官庁でも自治体でも、精神医療の所管は障害福祉担当であり、医療政策担当ではない。まずこの点で身体科と切り離されているのだが、これを知らない医師も多い。自殺予防医療を行うのは専ら精神科だが、自殺予防対策の国家予算に精神科医療が占める割合はごくわずかである。よく救急科に「なぜ精神科は医療対応が遅いのか、できないのか」と怒られるが、行政には正式に医療と認められていないのだ。
精神医療は患者をスティグマ化すると批判する人も多いが、精神医療自体もまた社会がスティグマ化してきたとも言える。デンマークのように日本の精神医療がスティグマから救われ、医療として社会に認められるのはいつの日か。
太刀川弘和(筑波大学医学医療系災害・地域精神医学教授)[精神医療][スティグマ][精神療法算定]