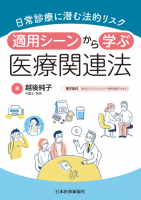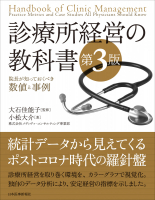お知らせ
【識者の眼】「東京都の民間病院財政支援の穴」薬師寺泰匡
病院経営という言葉があるが、実のところあまり裁量権がなく、経営と呼べるようなものではないと個人的には考えている。収益の中心を占める医療の価格は公定価格となっており、物価高騰や賃金上昇、インフレに対して価格転嫁することはできない。産業と社会保障の中間地点という絶妙なポジションであるが、近年は赤字病院の数が増え、病院の維持すら困難な状況となっている。
国が保険点数で調整するのか、何らかの財政支援を行うのか着目していたが、ここで東京都が総額300億円を超える規模の財政支援を、都内の民間病院向けに行うことを決めたと報道されていた。入院患者1人当たり1日580円を給付し、年間総額は約160億円、高齢の入院患者を受け入れるための病床確保料として約90億円、小児科、産科、救急医療の体制確保支援として約60億円を計上するとある。

時限措置ということで、国の動きを見ながらの延命処置とも言える状況かと思われるが、他の道府県への刺激となることを期待している。その一方で、他の道府県が追随することを考えると、財政支援の方法として少し詰めて考えてほしい部分があるので、その点を指摘しておく。
気になっているのは、「高齢の入院患者を受け入れるための病床確保料」である。このお金はどこに払われるのだろうか。2025年1月は特にインフルエンザが蔓延し、自宅や施設等からの救急搬送が増え、病床が埋まり搬送困難に陥る例が増加した。どうにかして病床を空けねばならないのは事実であるが、複雑な問題が絡んでいるので、病床確保料の分配先を決めるのは繊細さが求められる。
コロナ禍では、コロナ患者を受け入れるための空床をつくる場合の補償として補助金が配布された。同じようなスキームで、高齢の入院患者を受け入れるための空床確保を依頼し、その補償を行うのであろうか。しかし、補助金がなくなった瞬間に空床確保の努力が低減することが考えられるので、時限的なものではないほうがよいのではないかと考える。また、十分なインセンティブを働かせるためには、その病院の入院日当額以上の補償がなければならない。やや長期的な視点を持って制度を考える必要があるだろう。
さらに、最初の受け入れだけでなく、転院や退院先の確保も重要である。地域包括ケア病床や地域包括医療病棟は、空床を減らし、1日でも長く入院させておいたほうが経営的には有利になる。急性期病院から即時転院をさせようにも、後方病院が空床を確保せねば、転院が数日待ちになることはよくある。そうした回復期での退院についても、療養病棟や在宅診療、高齢者施設への転院・退院準備が整わなければ、空床はできない。経営上の考えとは別に、退院を困難にさせる要素がある。高齢の入院患者を受け入れるための病床確保料が、どこにどれだけ使われるのか、そしてどの程度影響するのか、着目したい。
薬師寺泰匡(薬師寺慈恵病院院長)[病院経営][財政支援][病床確保料]