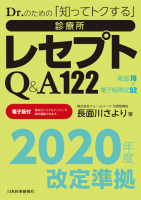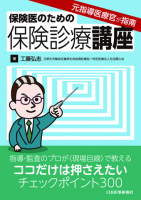お知らせ
■NEWS 後期高齢者への資格確認書交付の暫定的運用を26年7月末まで継続―厚労省
後期高齢者に対してマイナ保険証の保有状況に関係なく保険者が資格確認書を交付する暫定的運用の期限が2026年7月末まで1年間延長されることが4月3日、明らかになった。厚生労働省が同日の社会保障審議会・医療保険部会に報告した。
ITに馴染みのない高齢者ではマイナ保険証への移行に時間がかかるとの判断から、24年12月に健康保険証の新規発行が停止された際、後期高齢者については25年7月末までの間に限り、75歳への到達時や転居などで資格情報に変更が生じた場合にはマイナ保険証の有無を問わず、資格確認書を交付する暫定的運用が決まった。

だが、その後も後期高齢者のマイナ保険証利用率は低い状況が続いている上、後期高齢者の発行済み保険証は暫定的運用が終了する25年7月末に一斉に有効期限を迎える。そのタイミングで市町村窓口に資格確認書の交付申請が殺到する恐れがあるため、デジタルとアナログの併用期間を十分確保してマイナ保険証への円滑な移行を図る観点からも、現行の取り扱いを26年7月末まで継続することにした。
この日の部会では、(1)外来診療等におけるスマホ搭載対応、(2)顔認証付きカードリーダーの故障時等の対応―などについても報告があった。
■マイナ保険証のスマホ搭載、6月下旬頃から10施設程度で実証事業
(1)は、マイナ保険証を顔認証付きカードリーダーで読み取る代わりに、スマートフォンに搭載した電子証明書を汎用カードリーダーにかざすことで、オンライン資格確認を行う仕組み。6月下旬頃からスマホ搭載対応の環境(汎用カードリーダーの設置など)が整った医療機関・薬局10施設程度で実証事業を開始する。その結果を踏まえ、8月下旬以降、環境が整った医療機関から徐々に運用を開始していく予定。希望がある場合のみを対象とし、全医療機関への導入義務化は想定していない。
(2)は訪問診療時などにモバイル端末で患者のマイナ保険証を読み取る「居宅同意取得型」の仕組みを、顔認証付きカードリーダーの故障などで医療機関窓口ではオンライン資格確認ができない場合の対応として活用するもの。導入する場合は、国がモバイル端末の購入費用やレセプトコンピュータの改修費用を補助する。補助限度額は病院が41.1万円、診療所が12.8万円。補助金申請の受付開始時期は25年7月頃を予定している。