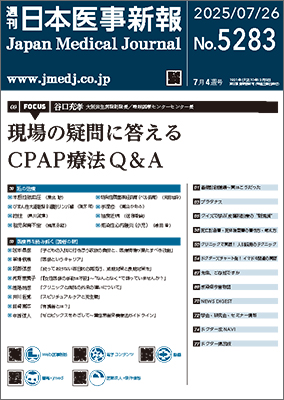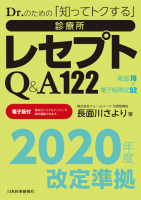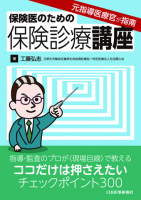お知らせ
■NEWS 診療側「コスト増のない純粋な診療報酬引上げを」―中医協総会
中央社会保険医療協議会・総会は4月23日、2026年度診療報酬改定に向けた共通認識醸成のため、医療機関を取り巻く状況について議論した。この中で診療側は改めて医療機関経営の危機的状況を訴えて診療報酬の引上げを求めたが、支払側は現役世代の保険料負担軽減の観点から医療の効率化・適正化の一層の推進を要請した。
厚生労働省が総会に提示した資料によると、医療法人の経常利益率の平均値および中央値は22年度から23年度にかけて病院、無床診療所、有床診療所の全ての類型で低下。最頻値(最も頻繁に現れる値)は全類型とも0.0%〜1.0%にとどまり、医療機関経営の窮状がうかがえる。

特に病院は事業費用が事業収益を上回る勢いで伸びたために収支が悪化。100床当たり損益を18年度と23年度で比較すると、事業収益が10.3%増加したのに対して事業費用の伸び率は14.7%となっている。金額ベースでは費用の50%以上を占める人件費の増加が及ぼした影響が最も大きいが、国内の賃上げの動向をみると医療関係職種の給与額は上昇傾向にこそあるものの、産業全体の平均には未だ追いついていない。
■支払側「保険料引上げは限界。医療の効率化を進めるべき」
こうした現状を踏まえ診療側の長島公之委員(日本医師会常任理事)は、「次期改定は他産業に負けない賃上げができるよう、医療機関の収支を改善するのが最大の課題だ」と強調。そのためには診療報酬上の手厚い評価が必須となるが、従来は点数の増点があっても人員配置の厳格化のようなコスト増につながる要件設定が併せて行われ、却って経営体力を削ぐことになっていたと振り返り、「コストを増やすことを前提とした形ではなく、純粋な形での診療報酬引上げが必要だ」と主張した。
これに対して支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は、「保険料の引上げは限界にきており、医療DXに本格的に取り組み医療の効率化を進めていくべきだ」と反論。診療報酬の引上げに慎重姿勢を示した。