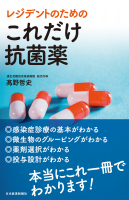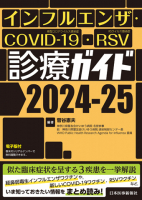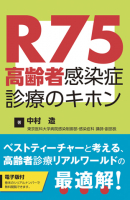お知らせ
【識者の眼】「COVID-19レプリコンワクチン〜My unanswered questions(Ⅲ)」西村秀一

前稿(No.5270)において、もしもレプリコンが体内に長期残存し、抗原を出し続けた場合に考えうる懸念を述べた。……が、じつはそれはレプリコンだけに限った話ではなく、通常のmRNAワクチン(以下、ワクチン)あるいはCOVID-19ワクチン全般の頻回投与にもつながりそうなquestionsであった。レプリコンとまったく同じではなく間歇的ではあるが、抗原がトータルで長く存在するという意味では、頻回のワクチン接種も似ているところがある。まずは、その中で、前稿で挙げた抗体依存性感染増強の可能性について考えてみる。
高齢者の多い施設で、入居者がほぼ全員6回以上ワクチンの接種を受けていても、爆発的アウトブレイクを見ることがある。高齢が故のワクチンの効果の低さなのか、あるいはほかの理由があるのか。高齢者に限らず、むしろワクチンを頻回接種したほうがCOVID-19への感染率が高いという報告もあるらしい。もし、本当にそういうことがあったとして、そこに抗体依存性感染増強が絡んでいる可能性はあるのかないか、というのが最近の筆者のquestionである。それを調べた研究があったらぜひ教えて頂きたい。

話は少し飛ぶが、それと関連して、そのようなアウトブレイクの話を見聞きするたびに、ワクチンの頻回接種の意義について確認が必要だと思う。抗原変異に対応した、あるいは抗ウイルス抗体価の時間経過による減衰に対応したboostingという説明がなされる。だが、たとえその感染阻止の効果が統計的に有意であったとしても、それが完璧でないことは経験上皆が知っている。そこで重症化阻止の出番である。だが、ワクチンの死亡阻止効果はここ1〜2年は如何ほどだったのか? 当初の素晴らしい効果を誇る報告はあるが、最近のデータはあるのか? たとえば高齢者施設間、あるいはその入居者間での6回接種の有無での比較でよい。最近は接種をしていない例も結構ある。できるだけ多くの例を巻き込んだup-to-dateの試験成績は、今後のワクチン接種を奨励する側の説明としてぜひ必要である。
さて、頻回接種についての懸念の話にもどる。レプリコンからは少し離れるが、mRNAを包む脂質に対する抗体ができたりしないのか、という話もある。そうした抗体ができるとすれば、中には自己抗体ができ、最悪の場合、自己免疫疾患に陥る人もいるのでは、という懸念である。ただ、そうしたことは、起きるとしても頻度としてきわめて稀と思われ、調べるにしても大規模疫学調査が必要な話である。ワクチンが世界中で使われて既に4年、ワクチン接種と自己免疫疾患の発生頻度の関連の有りなしを調べた研究があったら教えてほしい。
これまで3回にわたって筆者が知りたいと思ったことを書いてきた。一部を除き、どれも「可能性」の話でしかなく恐縮だが、誰かきちんとしたデータをもとに説明をして頂けたらと思う。
西村秀一(独立行政法人国立病院機構仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター長)[COVID-19][レプリコンワクチン]