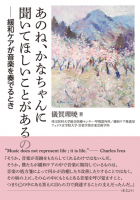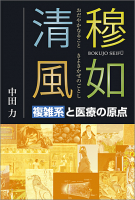お知らせ
EBMの誤解[炉辺閑話]
EBMは「科学的根拠に基づく医療」と訳される。EBMは、カナダのSackettらが確立した手法である。「エビデンスに基づき治療を行っています」はよく耳にする。しかし、これは本来のEBMの概念とはいささか異なっている。Shohjaniaはシステマティックレビューの結論のうち、約20%は2年で結論が覆されることを報告している。臨床研究による知見は常に暫定的と言える。エビデンスは常に暫定的であるからこそ、ガイドラインは一定の周期で改訂版を出さねばならない。日々の臨床から湧き出る「何かおかしい、これは良いという感覚」は、エビデンスの芽である。自ら毎日患者さんと接することで、患者さんはいくつもの「感覚」を教え授けてくれる。しかし、その感覚が普遍的なものか検証しないと、整形外科医はただの大工だと揶揄される。だからこそ整形外科医は、臨床研究のみならず、それを裏づける基礎研究を自らの手で行い、その成果を国際ジャーナルにアクセプトされる努力をしなければならない。追試により妥当性が検証されれば、ガイドラインが塗り替わることにもなる。
本来のEBMとは、最新のエビデンス論文を熟知することに加えて、医師のエキスパートオピニオン(経験的知識)および患者さんによる治療の選択、この3点を満たす医療がSackettの提唱したEBMの考え方である。Sackettはこう言っている。「EBM is not “cookbook”medicine. It's about integrating individual clinical expertise and the best external evidence」と述べている。

ガイドライン通りに医療をすればよいのであれば、医師の資格をとならなくても、本を読めれば医療ができてしまう。医師として誇りを持てるのはなぜか。「最新のエビデンスを熟知した上で、自らの医療知識と技術をもって、患者さんの人生を晴れやかなものにする」、その役割の一端を担えることに他ならない。